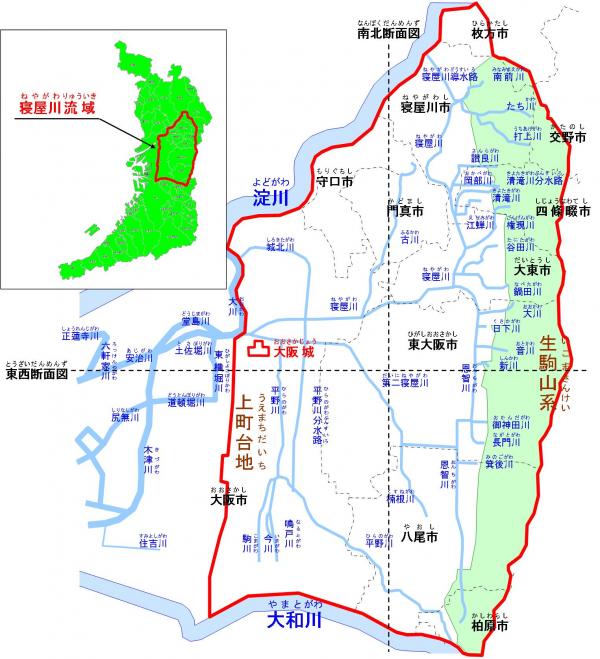目次
技術士は歴史に学ぶ ~後世につながる技術開発とは~
1969年5月26日に全線開通した東名高速道路は、工業・商業・農業・漁業などさまざまな産業の変革に関わり、また人々の暮らしを支えてきた高速道路である。沿線地域の活性化だけではなく,日本の物流を支える大動脈として日本経済の発展に貢献してきた。その長い工事の歴史であるが、それは未だ終わることがなく、昔も今も記録に残らない多くのエンジニアたちの尽力に支えられている。
日本の高速道路のプロトタイプ
全線にわたり周辺の地形に調和した優美な曲線で設計され、安全性を高めるための設計の修正及び設備の増強もなされた東名高速道路。それは、日本の高速道路のプロトタイプというべきものになった。
東名高速道路は、先に完成していた名神高速道路の建設経験を活かしたものであり、道路設計に関しては、一つの高みに達したといえる。
施工に関しても、合理化や現場主義が徹底され、高速道路施工の仕方が確立されていった。さらに、建設後には、設計や施工に関する要領がまとめられ、以後の高速道路建設の指針となった。
東名高速道路計画の経緯
戦前に始まった高速道路の調査。戦後には、東名高速道路の東京〜名古屋間の高速道路に関して、実業家の田中清一が中央道ルートを推した。その後にも、道路局内には東名と中央道を調査する部署ができた。
東名案と中央道案の激しい議論が起こる。しかし、どちらも性格が違う有益な道路ということから、1960(昭和35)年に、両道路とも建設法案が国会で成立し、東名高速道路は着工されることとなった。
「日本の道路は信じがたいほど悪い」と評した、世界銀行のワトキンス調査団。そんな道路の整備促進のため、財源の確保は急務とされた。
高速道の整備財源確保

1953(昭和28)年、当時の衆議院議員だった田中角栄らの議員立法で、揮発油税を創設して道路特定財源とすることが決まり、国道等の整備に当てられることとなった。
また、高速道の整備財源としては、1952(昭和27)年の有料道路制度の法制化による通行料金の財源化。さらに、1956(昭和31)年の日本道路公団の設立により、当面の建設財源として民間資金を導入できることとなった。
これらの財源を確保できたことにより、国道等の改良と高速道路の整備を同時に実行できることになった。さらに、高速道路ネットワークを一体として運営する、料金のプール制が導入される。
もともと大きな交通需要が見込める名神及び東名高速道路を先行して建設したことによって、その料金収入がそれ以降の日本の高速道路建設における大きな財源となった。
望ましい高速道路を求める熱意と情熱
名神の建設を経た日本の技術者は、東名高速道路を日本らしい高速道路へと昇華させ、日本の技術者が目指した「日本らしい高速道路」を完成させた。
周辺の地形に調和する滑らかな線形設計
約半分が直線となっていた名神と違い、東名の直線区間は全延長の4%と非常に短い。これは、周辺の地形に調和する滑らかな線形設計に努めた結果であり、透視図が活用された。
ヘリコプターやフォトモンタージュを使った景観設計には、費用がかかった。しかし、違和感なく橋梁の延長を短縮でき、大幅に工費を削減できるというメリットにもつながった。
名神における事故の分析などから、走行車線よりも追越車線の幅を広くすることで、円滑な追越を可能とした。さらに、多かった故障車にも配慮し、路肩幅も名神より広げた。
舗装法に関しても、名神でのひび割れ発生を受けてSN法に変更した。また、上層路盤にアスファルト安定処理材を標準的に使用することで、長期的な耐久性も向上することができた。
コンピューターでの設計と建築家たち
特に必要な場所については、大胆なラウンディングが徹底された。橋梁についてはコンピューターの発達で設計の自由度が増し、高速道路をまたぐオーバーブリッジにも、新たな形式が標準形として採用された。
東名高速道路の入り口には、都立砧公園の大木が沿道に移植または植樹された。また、名神に引き続き、菊竹清訓、黒川紀章、芦原義信といった著名な建築家が、サービスエリアを設計することとなった。
構造や設備の変更や追加
インターチェンジの形式は、料金所を1箇所にできるトランペット型が主流になっていった。さらに、安全に関しては、名神の維持管理の実績から、構造や設備の変更や追加が行われた。
事故時に対応するため、既存の仕様が変更され、新たな設備も設置された。沿道やトンネルに関しても、現在でも見られるような非常用設備の設置が行われた。
日本道路公団の技術部長であった田村幸久は、東名から道路システムの装置化が進み、どんどん性能が良くなることが始まったと言っている。
事実、名神と東名高速道路建設の経験を通じて、社内的には様々な要領が造られ、以後の高速道路の建設促進に繋がった。しかし、田村は、要領によりそれまでの望ましい高速道路を求める熱意と情熱が少し冷めてしまったと振り返っている。
寄せ集めの集団ならではの施工
役所や民間会社から来た寄せ集めの集団だった日本道路公団では、施工に関することを決める際には、現場でフルスケールの試験施工を実施して決めていく。
トライ&チェックの手法で
関東ロームでの試験盛土によって管理方法を変更したが、これは日本に多い土壌での施工方法のさきがけとなった。また、段差解消の課題に関しても、考案された新たな施工方法が試験的に採用された。
舗装の平坦性向上に関しては、「鉄道と同じように高速道路を走りながら新聞を読めるようにしたい」という目標のもと、新たな検査機器を作成し使用することで、100km/hでも安心して走れる舗装を実現させた。
若手エンジニアたちが検査機器を開発し、施工に関するシステムを作り、施工指導も行えたことは、寄せ集めの集団ゆえのメリットともいえる。
また、当時一般的ではなかった大規模施工のため、受注者が新たな大型機械を導入し試験施工で歩掛りなどを調査して積算するなどしながら、発注者と受注者が一体になって仕事を行った。

フォローアップシステムの導入
今までにあまり例がない曲線橋が多かったことから、大きな橋は指定橋梁として試験所と管理局で解析検証が行われた。
また、舗装に関しても、材料・舗装構成に応じた定点に計器を埋め込むなどの追跡調査が行われ、軟弱地盤も長期動態観測が実施された。
エンジニアたちの創意工夫
日本坂トンネルでの大出水の克服、由比地区では地域計画に合わせた海岸工事。薩埵高架橋での鋼桁を回転させる架設など、エンジニアたちの創意工夫が発揮された。
狭い工事ヤードで様々な工夫をしたことも、その後の都市内高速道路の建設に大きく役立った。現在の遠隔操作による無人化施工に繋がる技術も、この時に開発された。
当時の工事にエンジニアとして参加した元日本道路公団九州支社長の藤波督氏は、一人ひとりの技術者が現場で発想して試行錯誤してものを造っていく過程の積み重ねが大きな組織力になっていったと回想している。
道路も社会の進化に伴って進化を続ける必要があり、補修、改良、リニューアルなども、建設と同じように現場からの発想が大事で、記録に残らない個々の技術者の努力の積み上げが今の形を作っているのだと。
東名高速道路開通の効果
東名高速道路が整備されたことにより、東京–名古屋間の所要時間は半分に短縮された。また、利用台数は開通時の3倍以上に伸び、貨物輸送におけるトラック輸送へのシフトが見られた。
東京からの日帰りまたは宿泊観光圏も大幅に拡大し、長距離路線ができたことで高速バスの便数も大幅に拡大することとなった。
時代とともに変化する東名高速道路
道路は、造ったら終わりではなく、社会の進化に伴って継続的な進化を続ける必要がある。
顕在化した渋滞への対策
交通量の大幅な増大によって顕在化した渋滞への対策として、車線の増築やトンネルの改築が行われ、高速道路の死亡事故減少という効果が得られた。
さらに、2012(平成24)年に開通した新東名高速道路によって、リダンダンシーが向上。台風や高波の影響を受けやすい海岸付近で発生していた通行止めの解消にも役立っている。
防炎対策と民営化後の変化
167台の車両が延焼し7名の死者を出した日本坂トンネルの火災事故を教訓に、防災等級が見直された。そして、この防炎対策は全国の高速道路で実施されることとなる。
また、2005(平成17)年の民営化後には、魅力的で個性的なサービスエリアやパーキングエリア作りが行われるようになり、一般道側からのエリア利用も可能になった。

まとめ
1969(昭和44)年に全線開通した東名高速道路。日本の高速道路ネットワークは概成してきており、高速道路の機能や付加価値を高めるイノーベーションを進めていく時期になった。現代のそしてこれからのエンジニアたちは、先人たちが築いてきた日本の高速道路ネットワークを後世につなげていくという重大な任務を担っているのだ。