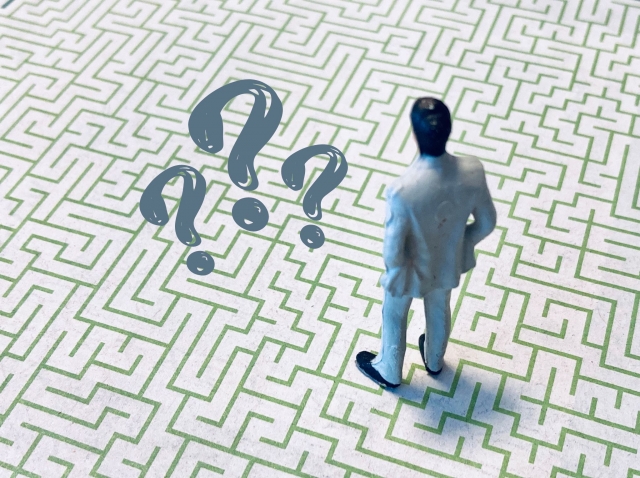目次
前編では、技術士試験の問題文を「デザインされた問い」として捉え、その意図を深く読み解き、本質的な「課題」を設定する「課題のデザイン」の重要性を論じました。後編では、設定した課題に対して、いかに説得力と深みのある「解」を導き出し、質の高い論文として構築していくかを探ります。このプロセスは、まさに自分自身の頭の中で「創造的対話」を繰り広げ、思考を編み上げていく知的作業にほかなりません。

① 「問い」の定義と技術士に求められる思考の型
本書は、探究の末に「問い」を以下のように定義しています。
問いとは、人々が創造的対話を通して認識と関係性を編み直すための媒体(メディア)である。
この定義は、技術士試験の論文作成プロセスを考える上で極めて重要です。技術士の論文は、単に知識を並べた「説明書」ではありません。出題者(社会)が提示した「問い」に対し、受験者が自身の持つ知識、経験、倫理観を総動員して「創造的対話」を行い、最適解を導き出す過程そのものを提示する「対話の記録」です。
本書で整理されている「質問」「発問」「問い」の違いは、技術士に求められる思考のレベルを示唆しています 。
- 質問:答えを知らない側が、知っている側に「情報を引きだす」行為です 。これは、論文作成の初期段階で、関連知識をインプットする行為に相当します。
- 発問:答えを知っている側(教師)が、知らない側(生徒)に「考えさせる」行為です 。技術士が後進を指導する場面では重要ですが、未知の課題に挑む試験の場では、この思考に留まっていては不十分です。
- 問い:問いかける側も、問われる側も「誰も答えを知らない」状況で、共に「創造的対話を促す」行為です 。技術士試験が扱う社会課題の多くは、唯一絶対の正解が存在しません。だからこそ、受験者にはこの「問い」の思考、すなわち、未知の状況で最善の解を探究する能力が求められるのです。
論文作成とは、この「誰も答えを知らない」状況を自覚し、自分の中の多様な視点(専門家としての自分、社会の一員としての自分、未来の世代の視点など)を対話させ、課題を解決に導くための「媒体」として文章を構築する営みです。
② 問いの基本サイクル ― 質の高い論文構成への応用
著者は、問いから新たな洞察と次の問いが生まれる循環プロセスを「問いの基本サイクル」と名付けています 。このサイクルは、そのまま優れた技術士論文の構成に応用することができます。
【問いの基本サイクル】
- 問いの生成と共有
- 思考と感情の刺激
- 創造的対話の促進
- 認識と関係性の変化
- 解の発見・洞察 → 新たな問いの生成
これを技術士論文の構成に当てはめてみましょう。
- ① 問いの生成と共有(論文の序論:背景と課題の提示)
- 試験問題という「問い」を共有されたものとして受け止め、その背景にある社会状況や技術動向を分析します 。
- そして、前編で述べた「課題のデザイン」を経て、「(問題文に示された状況に対し)真に解決すべき課題はこれである」と、自身が設定した「問い」を明確に提示します。これが論文全体の方向性を決定づける最も重要な部分です。
- ②,③ 思考の刺激と創造的対話(論文の本論:多面的な課題分析と解決策の立案)
- 設定した課題を、技術的側面だけでなく、経済性、社会・環境への影響、倫理的観点、法制度など、多面的な視点から分析します。これは、問いによって自身の「思考を刺激」し 、様々な角度から論点を洗い出すプロセスです。
- 次に、複数の解決策を立案し、それぞれのメリット・デメリット、リスク、実現可能性などを比較検討します。これは、頭の中で異なる意見をぶつけ合い、より良い結論を導き出す「創造的対話」に他なりません 。ここで重要なのは、アイデアを足し算するだけでなく、対立する要件(例:「安全性」と「経済性」)を乗り越えるような、より高次の解決策を模索することです。
- ④,⑤ 認識の変化と解の発見(論文の結論:最適解の提示と今後の展望)
- 対話(比較検討)を通じて、単なる技術論に留まっていた「認識」が、社会全体を俯瞰する視点へと「変化」します 。
- その上で、最も効果的かつ実行可能と判断される「解(最適解)」を具体的に提示します 。
- しかし、ここで終わりではありません。優れた論文は、その最適解を実行した際に新たに生じうるリスクや課題(=新たな問い) にまで言及し、それに対するモニタリング計画や改善策といった今後の展望を示すことで締めくくられます。これは、「問いが新たな問いを生む」 というサイクルを体現しており、技術者としての誠実さと深い洞察力を示す上で極めて効果的です。
このサイクルを意識することで、論文は単なる箇条書きの羅列ではなく、課題設定から解決、そして未来への展望まで一貫した論理でつながる、躍動感のある構成となります。
③ 問いのデザインの2つの手順と技術者の責務
本書は、実践的な「問いのデザイン」の手順を2段階で示しています 。これは、技術士がプロジェクトを遂行する際の思考プロセスそのものです。
- 課題のデザイン:問題の本質を捉え、解くべき課題を定める
- 技術士業務の最上流工程です。現象(問題)の背後にある本質を見抜き、取り組むべき方向性(課題)を正しく設定する能力が求められます 。
- プロセスのデザイン:問いを投げかけ、創造的対話を促進する
- 課題解決に向けて、具体的な計画を立て、関係者(ステークホルダー)との合意形成を図りながらプロジェクトを推進する能力です 。論文では、このプロセスをいかに考慮しているかを示すことが重要になります。
この2つの手順は、技術士の責務と深く結びついています。特に、社会構成主義 の考え方は、現代の技術者に不可欠な視座を提供します。社会構成主義とは、「現実」とは客観的に存在するものではなく、人々のコミュニケーションによって意味づけられ、合意されたものである、という考え方です 。
ある技術的課題に対する「解」は、専門家が一方的に提示するものではありません。それは、地域住民、行政、関連企業など、多様なステークホルダーとの**対話を通じて共に創り上げていく「合意された現実」**なのです。論文の中で、こうした合意形成プロセスの重要性に触れたり、具体的なコミュニケーション計画を提案したりすることは、技術者が社会の中で果たすべき役割を深く理解している証となります。

結論:技術士とは「社会のための問いをデザインする専門家」である
『問いのデザイン』の第1章を技術士試験の観点から読み解くと、技術士に求められる本質的な能力が浮かび上がってきます。
技術士とは、単に与えられた問題に技術的な「答え」を出す専門家ではありません。社会が直面する複雑で正解のない問題群の中から、その本質を見抜いて解くべき「課題」をデザインし、多様な人々と「創造的対話」を促進することで、社会全体にとってより良い未来(解)を構築していく専門家なのです。
試験論文は、そのための思考力と実践力を測るための場です。
- 問いを変えれば、答えは変わる 。問題文の捉え方一つで、論文の質は劇的に変化します。
- 問いは、思考と感情を動かす 。自分自身に多角的な問いを投げかけることで、思考は深まります。
- 問いは、新たな問いを生み出す 。一つの解に安住せず、常に次を見据える視点が、技術者としての成長を促します。
技術士試験への挑戦は、この「問いのデザイン」の思考法を体得する絶好の機会です。本書の知見を羅針盤として、ぜひご自身の思考プロセスを磨き上げ、合格、そしてその先にある技術者としての未来を切り拓いてください。
『問いのデザイン: 創造的対話のファシリテーション』:安斎 勇樹 (著), 塩瀬 隆之 (著) https://amzn.asia/d/hsSSExH