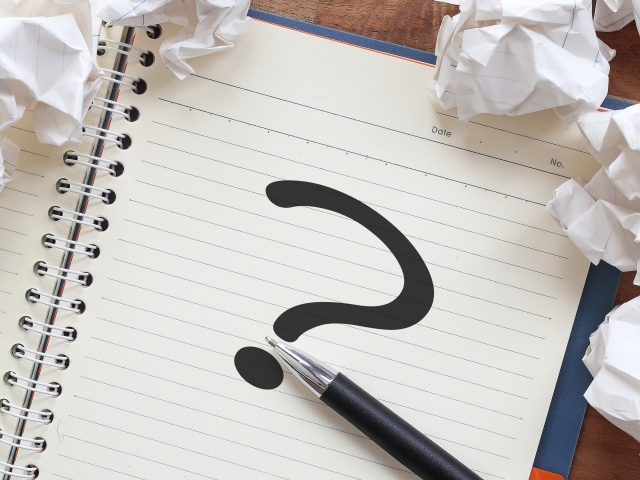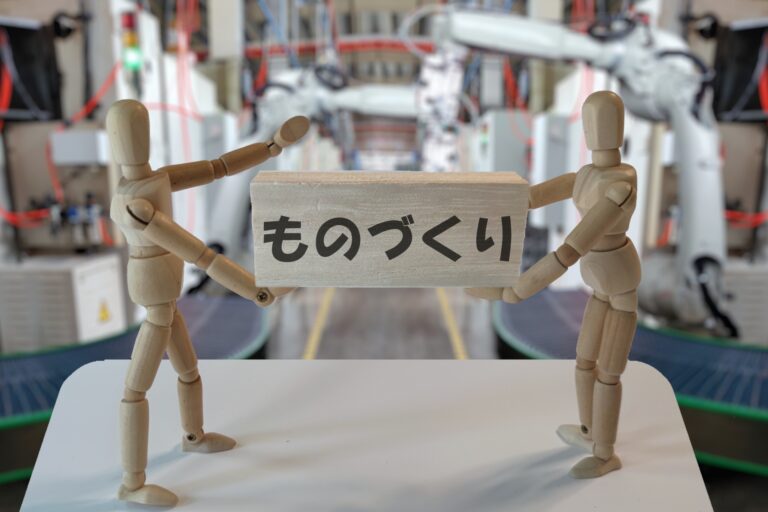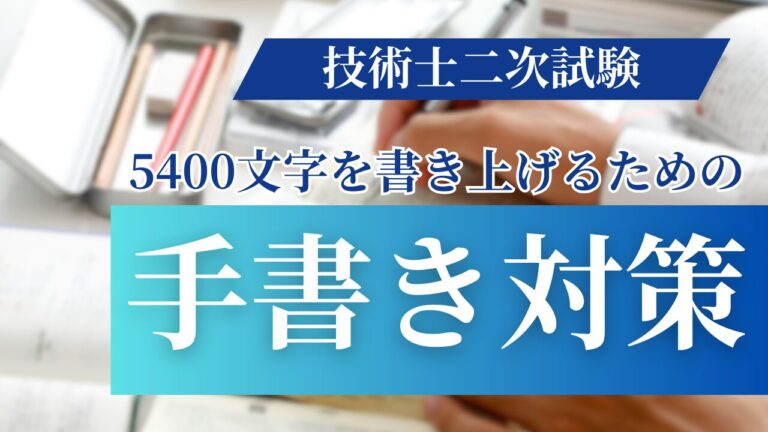技術士試験はエンジニアの試験ですが、文章の問題に対し文章で解答します。
そのため、以下3つの力をトレーニングする必要があります。
1)問題文を読み解く力⇒読解力
2)論文全体を論理的に考える力⇒論理的思考能力
3)読み手に伝わる文章を書く力⇒作文力
前回までは2回に分けて「論理的思考能力」について説明しました。
今回と次回は「作文力」について、トレーニング方法までまた、2回に分けてご説明します。

技術士論文の「血肉」となる。評価を劇的に変える『作文力』の本質(前編)
技術士第二次試験という頂を目指すエンジニアの皆様、こんにちは。 これまで2回にわたり、「読解力」で問題の意図を正確に捉え、「論理的思考能力」で解答の強固な骨格を組み立てる方法について解説してきました。読解力が**人体の「神経」として外部からの情報(問い)を受け取り、論理的思考がその情報を処理して「骨格」を形成するのだとすれば、今回からのテーマである「作文力」は、その骨格に「血肉」**を与え、生命を吹き込むプロセスに他なりません。
どんなに優れた骨格も、血肉がなければ、ただの骸骨です。人に感銘や納得を与えることはできません。同様に、どんなに鋭い分析や画期的な提案も、それを表現する「作文力」が伴わなければ、採点官にその価値を十分に伝えることはできず、正当な評価を得ることは困難です。
今回と次回の2回にわたり、この最終アウトプットの質を決定づける「作文力」について、その本質から具体的なトレーニング方法までを徹底的に解説します。
本稿(前編)では、まず**「技術士試験で求められる作文力とは何か」を定義し、「なぜそれが合否を分けるほど重要なのか」**を、不合格論文の典型例と高評価論文の共通点から解き明かしていきます。
Ⅰ:技術士試験における「作文力」とは何か?
まず、「作文力」という言葉の定義から始めましょう。一般的に作文力とは、「自分の考えや気持ちを、分かりやすく相手に伝える能力」とされます。しかし、技術士試験の文脈における作文力は、より限定的で、より戦略的な意味合いを持ちます。
技術士試験における作文力とは、**「技術者としての高い見識と専門的能力を、採点官という特定の読者に対し、限られた時間と紙幅の中で、一切の誤解なく明確に証明するための記述能力」**です。
これは、単に美しい文章を書く能力ではありません。以下の4つの要素が組み合わさった、総合的な技術(スキル)なのです。
- 論理的思考力(骨格の明示) 前回まで詳述した通り、思考の骨格がなければ、文章は成り立ちません。作文力は、その論理構造を文章の表面に明確に浮かび上がらせる役割を担います。
- 表現力・語彙力(的確な肉付け) 技術者として、専門用語を的確な文脈で、正確に使用する能力です。また、「〜の強化を図る」といった曖昧な表現を避け、「誰が、何を、どのようにするのか」を具体的に記述し、解像度の高い文章を構築する力も含まれます。
- 構成力(美しいプロポーション) 論文全体(600字詰×3枚)が、序論・本論・結論として一貫した流れを持っているか。各設問への解答が適切に配置されているか。段落と段落がスムーズに接続されているか。これら全体を設計し、バランスの取れた美しいプロポーションに仕上げる能力です。
- 読解力・想像力(相手への配慮) 書いた文章を、採点官の視点から客観的に読み返す能力です。「この説明で、専門外の採点官にも伝わるだろうか?」「ここで疑問を持たれないか?」「私の最もアピールしたい点は、明確に伝わっているか?」と、常に読み手の思考を想像し、先回りして疑問を解消していく配慮が求められます。
Ⅱ:なぜ「作文力」の欠如が不合格に直結するのか?
多くの受験者が、「内容は良いはずなのに、なぜか評価が低い」という悩みを抱えます。その原因のほとんどは、作文力の不足によって、思考の深さや知識の正確さが採点官に伝わっていないことにあります。作文力が低い論文には、致命的な「リスク」が潜んでいるのです。
リスク1:意図せず評価を下げる「減点表現」の罠
自分では気づかぬうちに、採点官に「この受験者は論理的に書く能力が低い」という印象を与えてしまう表現があります。代表的なものを5つ見ていきましょう。
- 一文が長すぎる(読解コストの増大) 「〜であり、〜のため、〜といった課題があるが、その対策としては〜することが重要で、」のように、読点(、)で文章を延々とつなげてしまうケースです。一文が長くなると、主語と述語の関係が曖昧になり、論理構造が崩壊します。採点官は、文章を解読するために余計な労力を強いられ、「結局、何が言いたいのか分かりにくい」というマイナス評価につながります。
- 主語と述語のねじれ(信頼性の失墜) 例:「私の考えは、〇〇という課題に対して、△△の導入による解決が期待される。」 この文では、主語「私の考えは」に対応する述語がありません。正しくは「私の考えでは、〜解決できると考える。」あるいは「〇〇という課題は、〜解決が期待される。」です。このような基本的な文法ミスは、論文全体の信頼性を根本から揺るがし、「技術者として、厳密な文章を書く能力に欠ける」と判断される大きな要因となります。
- 接続詞の誤用・乱用(論理の破綻) 接続詞は文と文をつなぐ重要な接着剤ですが、その選択を誤ると論理が破綻します。特に多いのが、本来は並列関係でしかない事柄を「したがって」で結び、因果関係があるかのように見せかけるケースや、思考停止で「そして」を連発し、単調な文章にしてしまうケースです。適切な接続詞を適切に使うことは、論理的思考を可視化する上で極めて重要です.
- 「こそあど言葉」の乱用(厳密性の欠如) 「これ」「それ」「あれ」といった指示語の多用は、文章の厳密性を著しく低下させます。「この課題」「その対策」と書かれても、何を指しているのかが文脈上100%明確でなければ、読み手は混乱します。技術論文では、指示語が指す対象が少しでも曖昧になる可能性がある場合、面倒でも具体的な名詞で繰り返し記述する正確性が求められます。
- 抽象的な表現(思考の浅さの露呈) 「体制を強化する」「連携を密にする」「意識を高める」といった表現は、聞こえは良いですが、具体性が皆無です。これらは技術者でなくとも言えることであり、「では、技術者として**『どのように』**強化するのか?」という最も重要な部分が欠落しています。このような抽象論に終始する論文は、思考が浅いと見なされ、評価は伸びません。
リスク2:思考の深さが伝わらない「コミュニケーション不全」
採点官は、あなたの頭の中を覗くことはできません。論文に書かれていることだけが、評価のすべてです。作文力の不足は、このコミュニケーションを阻害します。
- 説明不足の罠 自分にとっては自明の理でも、採点官にとってはそうとは限りません。特に、自身の専門分野の常識や、思考の前提となっている条件を省略してしまうと、論理の飛躍と捉えられます。「AだからCだ」と記述しても、読み手が「A→B→C」という思考プロセスを知らなければ、その結論に納得することはできないのです。
- 独りよがりの論文 結局のところ、作文力が低い論文の最大の問題は、**「読み手(採点官)意識の欠如」**にあります。自分の書きたいことを、自分の分かる言葉で、自分の都合の良い順序で書いているだけでは、技術士にふさわしいコミュニケーション能力があるとは言えません。「どうすれば、この見ず知らずの採点官に、自分の考えが最もスムーズに、かつ正確に伝わるだろうか?」という視点を持つことが、作文力の原点です。
結論として、作文力とは、**減点を防いで論文の信頼性を担保する「守りのスキル」**であると同時に、**自らの技術者としての能力を最大限にアピールするための「攻めのスキル」**でもあるのです。
Ⅲ:一読で納得!高評価を得る論文の「作文術」
では、逆に、採点官から「この受験者はよく分かっている」と高く評価される論文は、どのような作文術に基づいているのでしょうか。ここでは、すぐに実践できる4つの原則をご紹介します。
1. 結論ファースト(PREP法)を徹底する ビジネス文書の基本として知られるPREP法ですが、これは技術士論文において最強の構成術です。
- P (Point): 結論
- R (Reason): 理由
- E (Example): 具体例
- P (Point): 結論
設問(1)で「課題を3つ述べよ」と問われれば、解答の冒頭で「技術的課題は、①〇〇、②△△、③□□の3点である。」とまず結論を明記します。その後の段落で、①の課題、②の課題、③の課題をそれぞれPREPの構造で詳述していくのです。 この構成を守ることで、採点官は瞬時に「この受験者は問いに的確に答えている」と判断でき、ストレスなく論文を読み進めることができます。思考の明晰さをアピールする上で、これほど効果的な手法はありません。
2. 「一文一義」でシンプルに記述する 「一つの文には、一つの情報(意味)だけを込める」という原則です。これにより、前述した「一文が長すぎる」「主語と述語のねじれ」といった致命的なミスを構造的に防ぐことができます。 「Aであり、Bのため、Cである。」と書くのではなく、 「Aである。その理由はBだからだ。結果としてCとなる。」 というように、短い文を適切な接続詞でテンポよくつなぐことを意識しましょう。これにより、文章は明快になり、リズム感が生まれます。
3. 抽象から具体への転換を意識する 高評価論文は、例外なく具体的です。抽象的な表現を、具体的な「名詞」「動詞」「数値」に置き換える習慣をつけましょう。
- (△ 抽象)インフラの維持管理を効率化し、コストを大幅に削減する。
- (〇 具体)橋梁の点検にドローンとAI画像解析を導入することで、点検作業の人員を50%削減し、詳細調査が必要な箇所の特定精度を向上させ、ライフサイクルコストを**20%**削減する。
- (△ 抽象)関係者との連携を強化し、プロジェクトを円滑に進める。
- (〇 具体)設計の初期段階から施工業者も交えたBIM/CIM会議を週次で開催し、合意形成のフロントローディングを図ることで、現場での手戻りを30%削減する。
このように具体的に記述することで、あなたの提案は単なる理想論ではなく、実現可能性のある技術的な解決策として高く評価されます。
4. 専門用語を「効果的に」使用する 専門用語の使用は、技術者としての見識を示す上で重要ですが、使い方を誤ると逆効果になります。重要なのは、単に知っている用語をひけらかすのではなく、「その用語を使わなければ、この事象を的確に表現できない」という必然性のある場面で効果的に使うことです。 また、複数の専門分野にまたがるようなテーマの場合、採点官が必ずしもその用語に精通しているとは限りません。必要であれば、「〇〇(△△を実現するための技術)を導入する」のように、簡単な注釈を加えて読み手の理解を助ける配慮ができると、より高く評価されるでしょう。
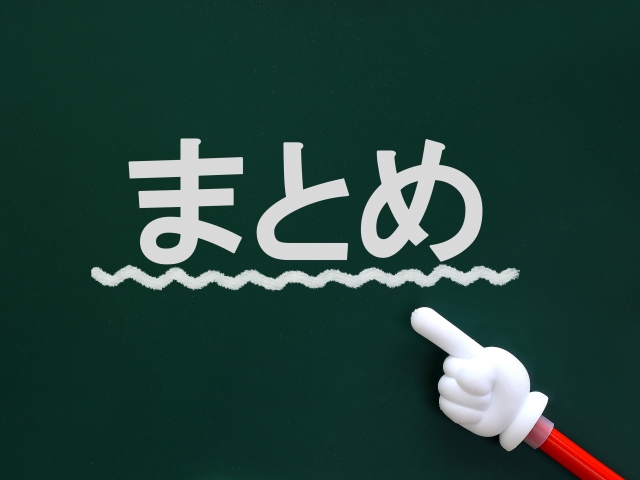
前編のまとめ
今回は、技術士試験における「作文力」の本質と、その重要性について解説しました。
- **技術士試験の作文力とは、**自らの技術的能力を、採点官に誤解なく証明するための戦略的な記述能力である。
- **作文力の欠如は、**意図せぬ減点を招き、思考の深さが伝わらないという致命的なリスクを伴う。
- 高評価の論文は、「結論ファースト」「一文一義」「具体性」「専門用語の的確な使用」といった共通の原則に基づいている。
作文力とは、論理的思考で組み上げた骨格に、採点官の心に響く説得力という血肉を与える、極めて重要な技術です。
では、これらの原則を身につけ、血肉の通った論文を書くためには、具体的にどのようなトレーニングを積めばよいのでしょうか。
次回、後編では**「作文力を飛躍的に向上させるための具体的なトレーニング方法」**について、実践的な練習問題も交えながら、さらに踏み込んで解説していきます。ご期待ください。