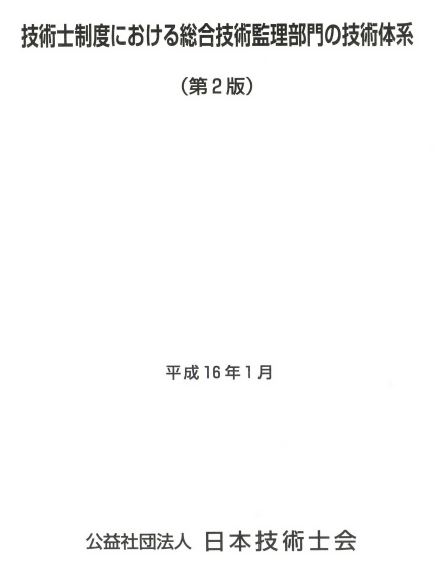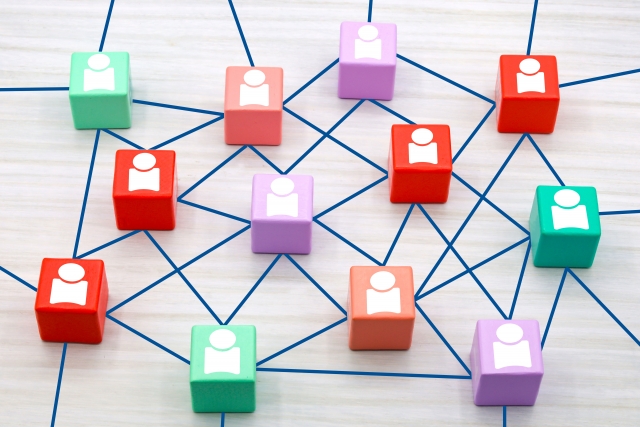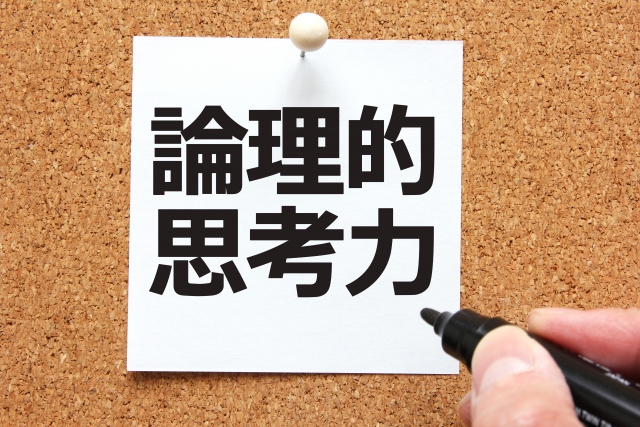総合技術監理部門は、択一で高得点を狙うのが合格の近道
「技術士制度における総含技術監理部門の技術体系」が廃刊になって、5年になります。
技術士会では費用削減のため、2019年から「キーワード集」という名のPDFを配布しています。
これは、5つの管理に分けられた、キーワードを羅列しただけの資料です。
全部で38ページの資料ですが、冒頭に目次と「まえがき」という、総合技術監理部門の説明があります。
キーワードの部分は35ページです。
キーワードの数はおよそ850、毎年微妙に追加と削除がありますが、総数は850程度で大きな変化はありません。
また、キーワードを縦に並べたり、横に並べたり、ネスティングの位置(深さ)を変えたりと落ち着きがありません。
2019から、2020に変わったときは、最初だったので比較的大きな変化でした。
しかし、2021から2022の変化は極わずかです。
はっきり言って、変える意味があるのか? と思っています。
Lock-On:二次試験講座では、「キーワード集2020」と「キーワード集2021」のどの部分から択一問題が出題されたのか、分析してみました。


上記は、総監受講者様に配布される資料の一部です。
「キーワード集2020」からは、令和2年の問題。
「キーワード集2021」からは、令和3年の問題が出題されています。
どちらも変更のあったところから、出題されているのではありません。
正直、出題のパターンは全く読めないです。
ただ、前年に出題されたキーワードは、連続で使われることがほとんどないということが分ります。
技術士会と文部科学省への問い合わせ
毎年、微妙に変化する「キーワード集」に関して、今後も毎年新たになるのかを、文部科学省の技術士分科会と技術士会に問い合わせしました。
どちらも回答は同じですが、以下、私が直接聞いた回答の要点です。
- 当面は基本的に毎年更新する。
- キーワードの並べ方に意味は無い。
- キーワードは、外部に委託して作成している。
- 文部科学省は、作成者を承認して依頼する。
- キーワード集作成者と択一試験の問題作成者は異なる。
- キーワードの並べ方、ネスティングの位置などは、作成者の個人的な考え方で決まる。
- キーワードの追加や削除も作成者の個人的な考え方による。
上記の通りです。
とはいえ、これが分ったからと意って、どのキーワードから出題されるのかは、分らないです。
Lock-On:二次試験講座では、総監受験者様のために、850のキーワードをすべて解説した、解説集を配布しています。
上の分析表とは異なるものです。
基本ベースは、「技術士制度における総含技術監理部門の技術体系」(通称青本)ですが、新たに追加されたキーワードは、調べて解説しています。
また、図表があった方が良いと思われるところは、図表も入れています。
この解説集と、Lock-On:二次試験講座のオリジナル択一問題40問×6回分=240問で択一対策をしっかり行ってください。
令和4年は、上記に加え、新たに40問を提供します。
口頭試験の結果は、まだ分らないですが、令和3年の試験では、9名が受験し、4名が受かっています。
また、受かっている方は、択一の点数が高いです。
択一試験は、結局のところ、暗記で対応するしかありません。
850のキーワード解説集は300ページを超え、文字数は25万文字もあります。
丸暗記は不可能ですが、択一問題⇒解説集⇒択一問題⇒解説集この繰り返しにより、キーワードは、確実に受講者さんの頭の中に定着します。
総監合格には択一試験で高得点を狙うのが近道
総合技術監理部門を受験する人は、一般部門の技術士を持っている方がほとんどです。
しかし、合格率は10%程度。
そもそも、択一試験は暗記の試験であり、そこに出てくるキーワードは、普段の仕事や業務であまり使いません。
例えば、以下のようなキーワードを一般のエンジニアが深く理解していることは極めてまれでしょう。
4.2 コミュニケーションと合意形成(情報管理)
コミュニケーションの方法
情報公開法
知る権利
開示基準
パブリック・リレーションズ(PR)
住民参加
ネット炎上
アカウンタビリティ(説明責任)
情報開示
開示請求
社会的受容(PA)
ステークホルダー
統合報告書
コミュニケーション論
言語/非言語コミュニケーション
マス・コミュニケーション
パーソナル・コミュニケーション
コミュニケーション技法
ファシリテーション技法
コーチング技法
カウンセリング技法
ネゴシエーション(交渉)技法
合意形成技法
また、論文試験は捉えどころがなく、どう書けば合格ラインを超えるのか分りにくいのです。
ですから、筆記試験はギリギリ合格として、択一試験で高得点を狙いましょう。
それが合格への近道です。
近年、総監部門で合格している方のほとんどが、28/40以上の点数を取っています。
100点満点なら70点です。
総監の合格ラインは60点であり、点数は択一と筆記の合算です。
択一で70点なら、筆記は50点でも合格です。
ですから、総合技術監理部門合格への近道は択一試験で高得点を取ることなのです。
Lock-On:二次試験講座では、総監のキーワード2022の全てのキーワードを解説しています。