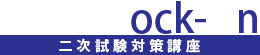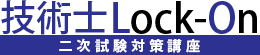昨日と今日で、伊丹 敬之(いたみ ひろゆき、1945年3月16日 – )は、日本の経営学者。一橋大学名誉教授、国際大学前学長、組織学会元会長。の名著『技術者のためのマネジメント入門-生きたMOTのすべて』を要約紹介したいと思います。
こちらから購入出来ます。
技術士二次試験の対策本ではないのですが、経営工学や総合技術監理部門の参考書としてとても有益です。
ロックオン講座の受講者さんには、ブログ記事をNotebookLMで解説したファイルも提供しています。
どうぞ活用してください。(文体は本の文体をそのまま踏襲しています)
伊丹敬之『技術者のためのマネジメント入門(生きたMOTのすべて)』第Ⅱ部要約|新規事業は「コンセプト創造」で決まる
第Ⅱ部が扱うテーマは「新事業を創る=コンセプトを創る」
第Ⅱ部の入口となる第6章は、技術者にとって最も痛い論点から入ります。日本企業は高品質なものづくりで勝ってきた。しかし、その強みがそのままでは勝てなくなった。だから新規事業が必要になった。ここまでは誰でも言いますが、著者が鋭いのは「なぜ日本企業は新規事業が弱いのか」を、技術や努力不足ではなく、思考様式と組織の構造の問題として説明する点です。
技術が良いことと、市場で価値になることは別物です。第Ⅰ部で整理された「技術→価値」への変換の話が、ここで「新事業」という最も不確実な領域に接続されます。第Ⅱ部は、技術者が新規事業に関わるなら、何を見て、何を設計し直すべきかを突きつけてきます。
1990年代以降に起きた「技術と市場の断絶」が新規事業を必然にした
著者は、1990年代以降の家電、クルマ、半導体などで顕著になった状況を「技術・市場の断絶」として捉えます。高度成長期の日本企業は、コア技術を磨き、性能競争で世界をリードしました。ところがコスト競争で追い上げられ、性能要素が成熟し、差が出にくくなると、技術起点だけでは差別化が崩れます。つまり「良いものを作れば売れる」という連鎖が切れたわけです。
ここで企業が逃げ切ろうとすると、既存事業の延長の改善に閉じこもります。ですが市場の構造が変わった以上、改善の積み上げでは追いつきません。だから新規事業が「選択肢」ではなく「必然」になります。第Ⅱ部は、その必然の正体を、数字や景気ではなく、競争のルール変更として描きます。
守破離で見ると、日本企業は「守」だけが強すぎる
第6章の核の一つが「守・破・離」です。著者はこれを精神論として扱いません。企業の行動様式の診断フレームとして使います。
守は既存技術・既存事業の強みを徹底的に活かす段階です。破は従来の枠組みを批判的に見直す段階です。離は既存事業とは異なる新しい価値体系を創造する段階です。日本企業は守が得意で、破と離が弱い。ここが著者の結論です。
「守が得意」というのは美点でもありますが、裏返すと、評価制度も会議も意思決定も、守で成果が出るように最適化されてしまっているということです。破や離をやろうとすると、途中で否定されやすい。つまり「個人の発想がない」のではなく、「破と離が生き残れない構造」がある、という話に落ちます。この視点は技術者に効きます。現場の努力でどうにもならない部分が、はっきり見えるからです。
図6-1の意味は単純で、売上が伸びても利益が落ちたから「次」を作らざるを得ない
著者は産業界全体の収益性低下を示します。売上高が伸びても利益率が落ちる。これは、国内需要の縮小だけでは説明できません。国際価格競争の激化、製品差別化の困難化、顧客ニーズの成熟化が重なり、儲けの源泉が枯れていく。結果として、既存事業の延命では限界が来る。だから新規事業が必要になる。
この整理が重要なのは、「新規事業をやるべきか」という議論を終わらせる力があるからです。やるかやらないかではなく、やらないと利益が保たない構造に入った、という説明になっているからです。
家電産業の変容は「テレビの価値がハードからソフト・コンテンツへ移った」という話
第6章で扱われる家電産業の例は、象徴として強いです。テレビは大型化・薄型化などのハードの進化が進みますが、付加価値の中心はユーザーインターフェース、コンテンツ、ソフトウェア側へ移ります。テレビ単体ハードの優位性が薄れ、パソコンやネットワークと機能統合が進む。つまり競争軸が変わったということです。
ここで痛いのは、日本企業が伝統的に強かった「ハード中心の競争力」が、構造変化の中で弱点になってしまう点です。技術が悪いのではありません。価値の置き場所が移ったのに、価値の置き場所を追いかけられなかった。この事実が、第Ⅱ部の「コンセプト創造」という言葉を、ただの流行語ではなく、実務の必須課題に変えます。
業際化が鍵になるのは、新規事業が「境界」でしか生まれにくいから
著者が強調する「業際化」は、いまの技術者が避けて通れないテーマです。新規事業は単一技術体系からは生まれにくい。ハード、ソフト、ネットワーク、サービス、デザインなど複数領域の知が融合して価値になります。つまり「境界領域(インターフェイス)」が主戦場になる。
ここで日本企業が弱いのは、縦割りで最適化された組織構造と相性が悪いからです。境界を攻めるには部門をまたがないといけない。ですが部門のKPIや権限が分断されていると、越境が止まります。だから業際化は「重要だ」で終わらず、「できる組織設計が必要」という管理の話に直結します。MOTが必要だという主張が、ここで現実味を持ちます。
コンセプトとは「市場がまだ気づいていない価値の論理」であり、製品アイデアではない
第6章の締めの定義が強いです。コンセプトとは、単なる製品アイデアではない。市場がまだ気づいていない新しい価値の論理であり、事業の哲学です。どの領域で、どんな価値体系を持ち、どの顧客に、どんな未来像を提示するのか。ここまで含めてコンセプトです。
だからコンセプトは、技術開発を牽引し、組織行動を統合します。逆に言えば、コンセプトがない新規事業は、途中で「何のためにやっているのか」が崩れ、組織が割れます。技術が良くても負ける典型パターンは、ここにあるという話です。
ソニーの事例が示すのは「ビジョンが先で、製品は後」という順序
著者はソニーの「デジタル・ドリーム・キッズ」構想を取り上げ、方向性の転換は個別製品の改良では生まれないことを示します。市場構造の変化を洞察し、未来の生活者像を描くことで初めて実現する。ビジョンがコンセプトを生む、という順序です。
技術者にとってここは重要です。技術から入ると、どうしても「できること」から考えます。しかし新規事業は「できること」ではなく「成立させる価値の論理」から組み立てる必要がある。著者はそこを突きます。
第Ⅱ部後半(第6章〜p.186)の要点は「統合知がないと新規事業は生まれない」
この範囲で著者が言い切っているのは、技術だけでは新しい価値は生まれないということです。技術を束ね、未来の市場を構想する統合知が必要になる。守に偏りすぎた日本企業は、新規事業の創造速度が遅れた。新事業の源泉は技術の延長ではなく、社会構造と生活者行動の変化の洞察にある。家電産業の重心移動は日本の強みを弱点化させた。業際化の理解なしにコンセプト創造は不可能である。コンセプトは価値の哲学である。これが骨格です。