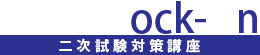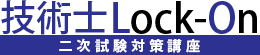今日と明日で、伊丹 敬之(いたみ ひろゆき、1945年3月16日 – )は、日本の経営学者。一橋大学名誉教授、国際大学前学長、組織学会元会長。の名著『技術者のためのマネジメント入門-生きたMOTのすべて』を要約紹介したいと思います。
こちらから購入出来ます。
技術士二次試験の対策本ではないのですが、経営工学や総合技術監理部門の参考書としてとても有益です。
ロックオン講座の受講者さんには、ブログ記事をNotebookLMで解説したファイルも提供しています。
どうぞ活用してください。(文体は本の文体をそのまま踏襲しています)
伊丹敬之『技術者のためのマネジメント入門』第Ⅰ部が示すMOTの本質
技術者のためのマネジメント入門の第Ⅰ部は、技術経営(MOT)を学ぶうえでの思想的な出発点を明確に示す構成となっている。本書はMOTを単なる経営手法や管理技術としてではなく、「技術」「知」「企業」「市場」の相互作用を理解するための知的枠組みとして提示している点に特徴がある。技術者がマネジメントに向き合う意味を根本から問い直す章であり、導入部でありながら極めて骨太な内容である。
技術とは何か|専門知識ではなく社会価値を生む行為
本書冒頭で著者は、「技術とは何か」という問いを真正面から取り上げる。ここで示される技術観は、工学的手法や専門知識の集合体という一般的な理解を超えたものだ。技術とは人間の欲求と創造性から立ち上がり、社会システムの中で価値を生み出す行為そのものである。技術は経済活動や社会生活の基盤であり、同時に経営判断や価値判断と不可分な領域に位置づけられる。
このように技術を捉えると、技術者の役割は単なる「専門技能の提供者」にとどまらない。自らの技術が社会や市場の中でどのような価値を持つのかを理解し、その意味を踏まえて主体的に判断する存在であることが求められる。本書はその前提を明確に打ち出している。
哲学(philosophia)から読み解く技術と知の関係
この技術観を支える思想的背景として、著者は哲学の語源である「philosophia(知を愛すること)」に言及する。知識が客観的に正しい情報の集積であるのに対し、哲学とは対象の意味や価値を深く問い続ける営みである。技術は知識の単純な応用ではなく、人間の能力を拡張し、新たな可能性を社会にもたらす創造行為である以上、技術者には哲学的態度が不可欠だと著者は説く。
ここで言う哲学的態度とは、抽象的な思索に耽ることではない。自らの技術が社会にどのような影響を与えるのかを意識し、その意味を問い続ける姿勢である。技術を持つ者は、その行使に伴う責任を引き受け、経営においても判断の主体となるべきだという強いメッセージが込められている。
MOTとは何か|技術の知を経営の知につなぐ枠組み
知と技術の関係は、歴史的・社会的文脈の中でも整理される。近代以降、科学知の発展とともに技術は高度に専門分化し、巨大組織の中で体系化されてきた。その結果、現代の技術者は自らの技術が社会全体の価値形成とどのように結びついているのかを見失いやすくなっている。
この断絶を埋めるための枠組みとして提示されるのがMOTである。MOTとは、技術を価値へと転換するプロセスを理解し、技術開発から事業化までを一貫して捉えるための知識体系である。著者はMOTを「技術の知を経営の知と結びつける体系」と定義し、技術者が自らの専門性と企業の市場戦略を接続するための道具だと位置づけている。
研究開発を阻む二つの壁|死の谷とダーウィンの海
企業の研究開発活動には、技術者が直面する典型的な障壁が存在する。本書ではそれを「死の谷」と「ダーウィンの海」という二つの概念で説明している。死の谷とは、基礎研究から製品化へ移行する段階で、多くの技術シーズが資金不足や組織的支援の欠如によって失われる領域である。ダーウィンの海とは、製品化後に市場競争の淘汰圧によって多くの製品が生き残れない状況を指す。
MOTは、この二つの難所を越えるための実践的知識体系である。研究開発の出口戦略を描き、技術ポートフォリオを構築し、事業化プロセスを可視化することによって、技術を市場価値へと導く道筋を示す役割を果たす。
日本のものづくり文化と技術経営の限界
本書は、日本のものづくり文化についても丁寧に論じている。日本の製造業は、現場の知や熟練技能、改善活動を重視し、人と人との協働の中で高い品質を実現してきた。「作る」と「創る」を一体として捉える姿勢は、日本企業の大きな強みであった。
しかし、グローバル競争の激化やデジタル化、サービス化が進む現代において、この強みがそのまま競争優位として機能しなくなっている現実も指摘される。現場力への依存だけでは、市場の急激な変化や技術の高度化に対応しきれない。企業全体として技術戦略を描き、価値創造の構造を明確にする必要性が高まっている。
暗黙知を価値に変える|TPMサイクルと技術の言語化
そのために重要となるのが、技術者による「言語化」である。企業内には暗黙知として蓄積された技術的知識が数多く存在するが、それを抽象化し、分析し、共有しなければ経営資源にはならない。著者は、技術・市場・製品の相互作用を循環構造として捉えるTPMサイクルを示し、技術起点で価値創造を進めつつ、市場の声を次の技術へと反映させる連続的プロセスの重要性を説いている。
市場理解が技術を変える|MOTにおけるマーケティング思考
第Ⅰ部後半では、市場理解と顧客価値の把握が技術者にとって不可欠であることが詳述される。マーケティングは「売るための工夫」ではなく、顧客価値を創造するための思考体系である。STPや4Pといった枠組みは、技術者が自社技術の価値を客観的に捉えるための道具として位置づけられる。
製品は単なる物理的構造ではなく、中核価値・実体価値・付随価値の組み合わせによって成り立つ。性能が高いだけでは顧客価値は生まれない。この点を理解しない限り、技術と市場のズレは埋まらない。
製品価値の正体|iPodに学ぶ価値の総合設計
iPodの事例は、その象徴的な例として紹介される。iPodの成功は、技術性能の高さだけでなく、デザイン、操作性、プラットフォーム、ライフスタイル提案といった複数の価値要素を統合した点にある。顧客価値は、技術を核としながら総合的に設計されるものであり、技術者はその全体構造を理解する必要がある。
組織と技術の関係|越境する技術者がイノベーションを生む
さらに本書は、組織と技術の関係にも踏み込む。組織は技術の実行力を左右する仕組みであり、技術者には専門領域を越えて連携する越境能力が求められる。知識がサイロ化した組織からは、新しい価値は生まれない。技術者は実装者にとどまらず、意思決定に参加する主体としての判断軸を持つべきだと著者は強調する。
第Ⅰ部が伝える核心|技術の価値を決めるのは技術者自身である
第Ⅰ部全体を貫くメッセージは明確である。技術の本質を理解し、それを市場価値へと転換する主体は技術者である。技術者が自らの役割を狭く捉えれば、技術は経営に生かされず、企業は競争力を失う。逆に、技術者が価値創造の主体として立ち上がれば、企業は持続的にイノベーションを生み出せる。
第Ⅰ部は単なる導入ではない。技術者が経営に関わるための思考の背骨を形づくる章であり、MOTの基礎思想を網羅的に提示する重要なパートである。