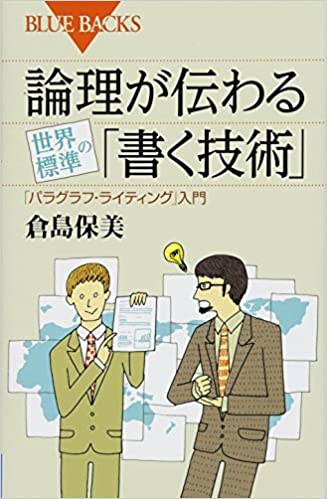目次
序章:なぜ技術士試験は「掴みどころがない」のでしょうか
技術士第二次試験、特に必須科目Ⅰや選択科目Ⅲの論文試験の学習に初めて向き合ったとき、多くの受験者がまるで濃い霧の中にいるような感覚に陥ります。「一体、何をどう勉強すればよいのか、皆目見当がつかない」。これは、決してあなた一人が感じる不安ではありません。
目の前にある問題文は、一見すると日本語で書かれています。しかし、その問いは抽象的で、どこに論点を定め、何を根拠に論を展開すればよいのか、その「掴みどころのなさ」に戸惑います。大学入試までの学習のように、明確な一つの正解が用意されているわけではありません。参考書を読み、キーワードを暗記しても、それだけでは合格論文という名の建造物を組み上げることはできないのです。この漠然とした不安こそ、すべての受験者が最初に直面する巨大な壁です。
この状況を喝破する、分野も時代も全く異なる一冊の本があります。大学受験古文の世界で長年バイブルとして読み継がれてきた、小西甚一氏の『古文研究法』です。その「はじめに」で、著者は国語という教科の本質を次のように喝破しています。
「国語という学科は、一見するとつかみどころがないが、実はきわめて筋途の立った勉強を要する学問である。」
この言葉は、驚くほど正確に技術士試験の本質を射抜いています。技術士試験とは、専門知識の量を問う試験ではありません。それは、与えられた複雑で曖昧な状況に対し、いかに「筋道を立てて思考し、論理的に説明できるか」という、技術者としての根幹をなす能力を問う試験なのです。
本稿では、この小西氏の教えを羅針盤とし、技術士試験における「読解力」を根本から鍛え上げるための方法論を探求していきます。前編では、合格論文の骨格となる「思考の筋道」をいかにして構築するかに焦点を当てます。

第一章:「筋道」こそが技術者の思考そのものです
小西氏は、筋道のない解釈を「切れないナイフで、かたいビフテキをごしごしやるような解釈」と痛烈に批判しました。思考に明確な論理の筋が通っていなければ、それは解釈とは呼べず、単なる言葉の摩擦に過ぎない、というのです。
この比喩は、技術士の論文評価にそのまま当てはまります。多くの不合格論文に見られる共通点は、まさにこの「筋道の欠如」です。
- 関連キーワードを無秩序に羅列している
- 課題と原因、原因と対策の間に論理的なつながりがない
- 序盤で掲げたテーマと、結論が食い違っている
これらは、最新の技術動向や政策に関する知識をどれだけ盛り込んでいたとしても、評価されることはありません。なぜなら、読み手である試験官は、受験者の知識の断片を見たいのではなく、「一つの課題に対して、原因を分析し、解決策を導き、その効果を検証する」という一貫した思考プロセスを確認したいからです。それこそが、技術者に求められるコンピテンシー(資質能力)の中核、特に「マネジメント」「評価」「コミュニケーション」能力の証明に他なりません。
筋道を立てるとは、思考を順序立てて積み重ね、構造化することです。技術士論文の答案構成に置き換えれば、以下のプロセスがその“筋道”となります。
- 設問の正確な読解(題意の把握):出題者は何を、どのような立場で、何を根拠に求めているのかを特定します。
- 多面的な課題の抽出:現状分析に基づき、解決すべき最も重要かつ本質的な課題を複数設定します。
- 課題の根本原因分析:なぜその課題が生じているのか、背景にある要因を深掘りし、因果関係を明らかにします。
- 具体的かつ実現可能な解決策の立案:分析した原因を直接的に解消するための技術的、管理的方策を複数提案します。
- 解決策の評価(効果とリスク):提案した方策がもたらす波及効果と、新たに生じうるリスクや懸念事項を客観的に評価します。
- 社会への貢献の明示:一連の技術的提案が、最終的に社会全体の持続可能性や国民の安全・安心にどう貢献するのかを論じます。 この一連の流れを、一本の強靭な論理の糸で貫くこと。それこそが、どんなに抽象的なテーマであっても、揺るぎない説得力を持つ論文を構築するための唯一の方法なのです。
- 問題文を解剖する三つの視点 ― 小西流「三系統の理解」の応用 では、どうすればその強靭な「筋道」の起点となる、正確な問題文の読解が可能になるのでしょうか。ここで再び、小西氏の慧眼が光ります。彼は、古文を深く理解するためには三つの系統があると説きました。それが「語学的理解」「精神的理解」「歴史的理解」です。この分析アプローチは、技術士試験の問題文を解剖し、その深層構造を読み解くための極めて強力なツールとなります。
第二章: 語学的理解:設問構造を精密に読み解く力
小西氏は「どうせ日本語だから――。こんな考えが、高校生諸君の頭のどこかにこびりついていやしないか」と警鐘を鳴らします。技術士試験の受験者もまた、「長年、技術文書を読んできたのだから読解には自信がある」と考えがちです。しかし、小西氏が「正確な理解以外は理解ではない」と断言するように、技術士試験で求められるのは「だいたいの理解」ではなく、設問の要求をミリ単位で捉える精密な読解力です。
語学的理解とは、問題文を構成する一つひとつの単語、接続詞、文末表現が持つ意味と役割を、構造的に分析する力です。
- キーワードの定義を捉える:「〜を推進するため」「〜の課題を抽出し」「〜の留意点を述べよ」といった言葉の定義は何か。「推進」と「普及」はどう違うのか。「課題」と「問題点」はどう使い分けるべきか。これらの言葉を自己流に解釈せず、出題者の意図通りに受け取ることが第一歩です。
- 制約条件を絶対視する:「技術者としての立場で」「〜の観点から」「最も重要と考える課題を3つ挙げ」といった制約条件は、論文の方向性を決定づける絶対的な命令です。これを見落としたり、無視したりした瞬間に、論文は題意を外れ、評価の対象外となります。
- 文章の論理構造を分解する:「Aを踏まえ、Bについて、Cの観点から述べよ」というような複雑な構文は、一つひとつの要素に分解し、それらの関係性を図式化する必要があります。「A(背景・前提)→ B(中心テーマ)→ C(分析の切り口)」という構造を正確に把握することで、初めて論述の全体像が明確になります。
この語学的理解は、論文全体の設計図を描くための基礎工事に等しいです。この工事が疎かになれば、その上にどれだけ立派な知識を積み上げても、脆弱な構造物しか生まれません。
第三章: 精神的理解:出題者の意図を洞察する力
正確な語学的理解ができたとしても、それだけでは十分ではありません。小西氏が言うように、「ほんとうに正確な語学的理解は、精神的理解の裏づけがあってこそ、はじめて期待される」のです。精神的理解とは、文章の表面的な意味を超えて、その背後にある作者(出題者)の意図や価値観を深く洞察する力です。
技術士試験において、この力は「なぜ、今、このテーマが出題されたのか?」という問いを自らに立てることに集約されます。
- 社会的背景との接続:そのテーマは、近年のどのような社会情勢(例:大規模災害の頻発、インフラの老朽化、カーボンニュートラルへの要請、DXの加速)と密接に関連しているのでしょうか。国の最新の政策(例:国土強靭化基本計画、インフラ長寿命化計画、グリーン成長戦略)の中で、どのように位置づけられているのでしょうか。この背景を理解することで、課題設定の解像度が格段に上がります。
- 技術者への期待を読み解く:出題者は、このテーマに対して技術者にどのような役割を果たすことを期待しているのでしょうか。単一の専門分野に閉じた技術論か、それとも分野を横断する俯瞰的な視点か。経済性や環境配慮、住民合意形成といった多様な価値観を統合するマネジメント能力を求めているのではないでしょうか。出題者の期待を推し量ることで、論文が目指すべきゴールが明確になります。
この精神的理解は、論文に「魂」を吹き込む作業です。単なる無味乾燥な技術報告書ではなく、社会の課題解決に貢献しようとする技術者としての高い倫理観と使命感を示すことができます。

第四章: 歴史的理解:技術・社会的背景を立体的に把握する力
小西氏は「自分がいま日本のどの辺を走っているかを知ることは、地図が頭のなかになければ、ぜったい出来ない」と述べ、その地図にあたるものが歴史であると説きました。これは、技術論においても全く同じです。ある技術や社会課題を論じる際、その歴史的変遷を理解しているかどうかで、議論の深みが全く異なってきます。
歴史的理解とは、対象となるテーマを時間軸の中に位置づけ、その成り立ちや発展の経緯を踏まえて立体的に捉える力です。
- 技術開発の文脈を理解する:現在主流となっている技術は、過去のどのような技術的課題を乗り越えて生まれてきたのでしょうか。過去にはどのような失敗があり、そこから我々は何を学んだのでしょうか。例えば、耐震設計基準の変遷は、過去の大地震の教訓そのものです。この文脈を理解することで、提案する解決策に歴史的な説得力と重みを持たせることができます。
- 政策や社会制度の変遷を捉える:現在のインフラ整備や環境政策は、過去の経済成長や公害問題、法改正の歴史の上に成り立っています。なぜ今、維持管理の重要性が叫ばれるのでしょうか。それは高度経済成長期に集中的に整備されたインフラが一斉に更新時期を迎えているからです。この歴史的背景を冒頭で示すだけで、課題設定の妥当性が格段に高まります。
これら「語学的」「精神的」「歴史的」の三つの理解は、それぞれが独立しているわけではありません。富士山の頂を目指すのに複数の登山ルートがあるように、これら三つのアプローチは相互に深く関連し合い、最終的に「問題の本質を正確に捉える」という一つの目的に収斂します。
読解力とは、単に文字を追う力ではないのです。それは、問題文という氷山の一角から、その水面下に隠された巨大な構造、意図、そして歴史的背景までをも読み解き、自身の思考の出発点となる揺ぎない「設計図」を描き出す力なのです。
註:小西甚一(こにし じんいち、1915年〈大正4年〉8月22日 – 2007年〈平成19年〉5月26日)は、日本の文学者(日本中世文学、比較文学)。文学博士(東京文理科大学・論文博士・1954年)。筑波大学名誉教授。
古文研究法 (ちくま学芸文庫 コ 30-2)
https://amzn.asia/d/6wY9AwH