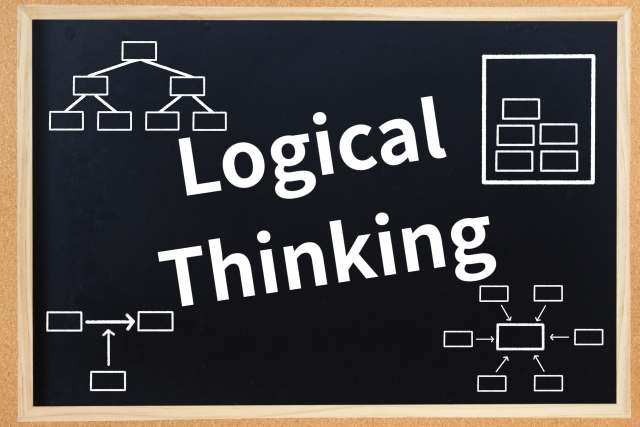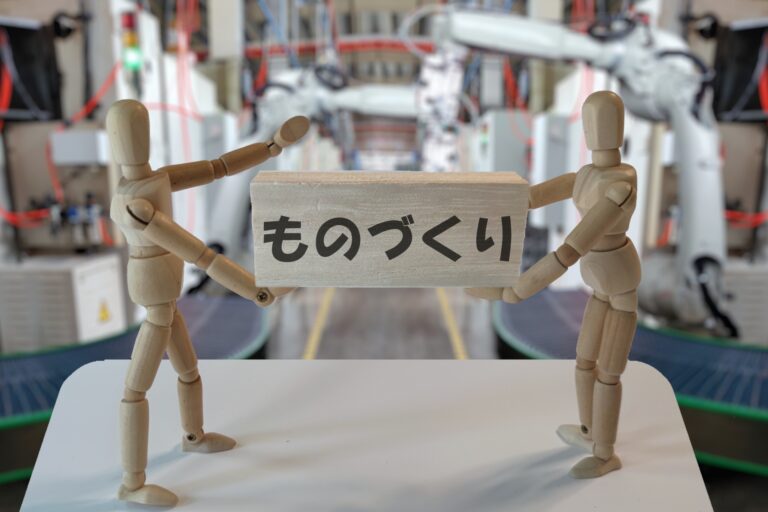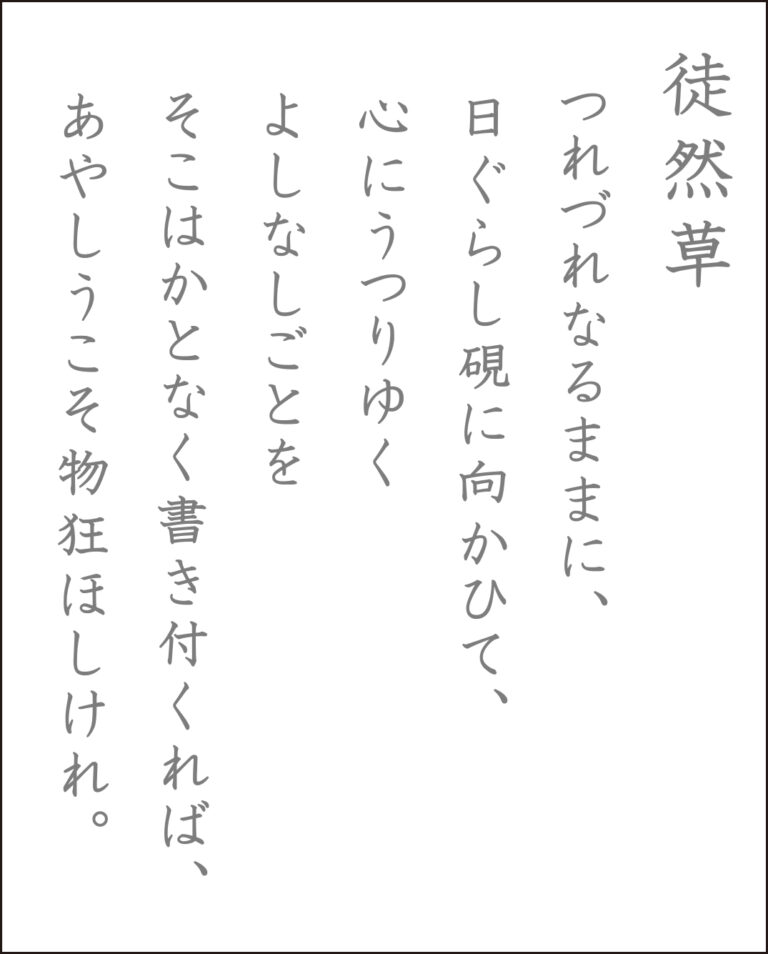技術士試験はエンジニアの試験ですが、文章の問題に対し文章で解答します。
そのため、以下3つの力をトレーニングする必要があります。
1)問題文を読み解く力⇒読解力
2)論文全体を論理的に考える力⇒論理的思考能力
3)読み手に伝わる文章を書く力⇒作文力
前回は「論理的思考能力」について説明しました。
今回は「論理的思考能力」の後編です、より深く説明します。
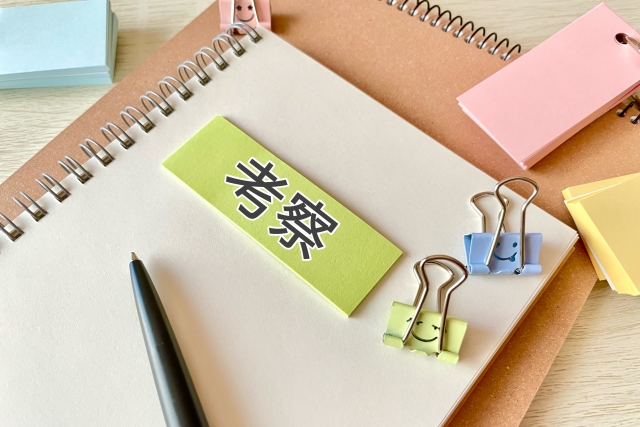
技術士試験に直結する「論理的思考能力」を鍛える(後編)
1. 前編の振り返りと後編の位置づけ
前編では「論理的思考能力」の基本構造を整理し、結論と根拠の関係を明確にしながら答案を破綻なく組み立てるための原則を解説した。演繹・帰納・仮説推論の型、題意の把握、多角的視点の構造化、数値根拠の活用、反論処理などを扱った。後編では、これらの土台を実際の答案設計に落とし込み、段落構成や接続語の使い方、答案の流れをどう仕上げるかに焦点を当てる。試験本番を想定した「使える技術」にまで落とし込むことが目的である。
2. 答案構成の全体像
技術士試験の答案は、概ね次の流れを意識して設計すると破綻しない。
①導入部:設問の趣旨と評価軸を短く示す
②課題提示部:現状の問題点や課題を具体的に整理する
③原因分析部:課題が生じる要因を整理し、因果を示す
④対策提示部:原因に対応する具体的な打ち手を提示する
⑤効果・展望部:対策の実施による効果や期待される成果を述べる
⑥結論部:答案全体を総括し、再度主張を明確化する
これは「課題→原因→対策→効果」の因果の流れをベースにしたものだ。導入と結論は全体の枠を与え、本文は三段構成(課題・対策・効果)で展開すると、採点者にとって非常に読みやすい。
3. 導入部の役割
導入部は短く、しかし答案の方向性を決める極めて重要なパートだ。設問の題意を自分の言葉で言い直し、答案全体の「評価軸」を提示する。例えば「老朽化した社会資本の更新における課題と対策を述べよ」という設問であれば、「本稿では経済性・安全性・持続性の観点から課題を整理し、更新を円滑に進めるための対策を論じる」と書く。この一文で、採点者は答案の軸を把握でき、後の展開も受け入れやすくなる。
4. 課題提示部の設計
課題提示部では、現状と理想のギャップを具体的に描き出す。ここで注意すべきは「抽象的な標語を書かない」ことだ。例えば「人材不足が課題」と書くだけでは弱い。「ベテラン技術者の大量退職により、設備管理技術の継承が進まず、事故リスクが高まる」と具体化すれば、次に書く原因や対策と自然につながる。課題は必ず「誰にとって」「どんな不一致が生じているのか」という形で表現するのが望ましい。
5. 原因分析部の精度を高める
課題を列挙したら、それが生じている原因を明示する。ここでは「なぜ」を3回掘り下げる習慣が役立つ。例えば「人材不足」という課題の原因は「若手採用の停滞」であり、さらに「労働条件が他産業に比べて魅力に乏しい」ことに起因している、といった具合だ。原因を掘り下げると、対策が具体化し、答案の論理が飛躍しなくなる。
6. 対策提示部の作り方
原因分析に対応する形で対策を提示する。重要なのは「課題と原因に対応していること」である。課題が「更新費用が不足している」なら、対策は「ライフサイクルコストを踏まえた投資計画」となるべきで、いきなり「新技術導入」では飛躍が生じる。答案の段落ごとに「課題→原因→対策」の因果が閉じていれば、論理的構成は自然と強固になる。
7. 効果・展望部の説得力
対策を書いたら必ず「効果」や「展望」に触れる。ここを省略すると答案は「提案止まり」になり、評価が下がる。効果はできるだけ定量化する。例えば「更新優先度をリスクベースで決定することで、破裂事故件数を5年で30%削減できる」といった表現だ。もし定量が難しければ、「安全性が向上し、利用者の安心感を高める」「社会的信頼を回復する」など、社会的価値に言及することでも十分に効果を補強できる。
8. 結論部のまとめ方
結論部では答案全体を短く総括し、導入で示した評価軸と結論を再度一致させる。結論は新しい情報を加えず、「本稿では〜と整理し、〜の効果を示した。これにより〜が期待できる」とシンプルに書く。採点者は最後の段落を重点的に読む傾向があるため、ここで答案全体の整合性をもう一度強調することが重要だ。
9. 接続語の使い方
論理的に答案をつなぐためには、接続語の選び方も重要になる。
- 原因を示すとき:「なぜなら」「その理由は」
- 具体例を示すとき:「例えば」「具体的には」
- 対比を示すとき:「一方で」「しかし」
- 結論をまとめるとき:「したがって」「以上より」
接続語を意識的に配置することで、論理の流れが滑らかになり、採点者が迷わず読み進められる。
接続詞の注意点として「そして」は使用不可であるということ。
接続詞「そして」は、会話でも文章でも頻繁に使われる便利な言葉だが、多用すると文章の質を低下させる要因となる。洗練された文章を目指す上では、その使用を意識的に避けるべきである。理由は主に**「単調さの誘発」と「論理関係の曖昧さ」**の2点にある。
①単調さと冗長性を招く
「そして」は非常に汎用性が高く、単純に事柄を付け加える際に無意識に使いやすい。しかし、その手軽さゆえに連続して使用すると、「Aをした。そしてBをした。そしてCをした。」といった平板な文章構造になりがちである。
このような単調な繰り返しは、文章のリズムを損ない、読み手に稚拙でくどい印象を与える。特に、事実や出来事を時系列で単純に羅列する際に、この傾向は顕著になる。文章に深みや変化を持たせるためには、安易な「そして」の使用を控えなければならない。
②文と文の論理関係を曖昧にする
「そして」が持つ基本的な意味は、前の事柄に後の事柄を並列・累加(付け加える)することである。しかし、本来はより明確な論理関係を示すべき場面でも、便宜的に使われてしまうことが多い。
例えば、以下のような文脈を考えてみよう。
- 原因・結果: 「雨が降ってきた。そして彼は傘をさした。」
- この文脈では「雨が降ってきたために、彼は傘をさした」という因果関係が明確である。適切な接続詞は「そのため」「そこで」である。
- 逆接・対比: 「彼は懸命に努力した。そして失敗した。」
- 努力が報われなかったという逆説的なニュアンスが強い。より意図を明確にするなら「しかし」「だが」が適切である。
このように、「そして」は**「追加」「原因」「結果」「逆接」など、多様な文脈で使われ得るが、それ自身の意味は弱いため、文と文の間の論理的なつながりを曖昧にしてしまう**。書き手の意図が読み手に正確に伝わらず、誤解を生むリスクもある。
文章の説得力を高めるには、前後の文脈を精査し、その関係性を示すのに最もふさわしい接続詞を選択することが不可欠である。「そして」を使いたくなった時は、一度立ち止まり、**「また」「さらに」「そのため」「しかし」**など、他の接続詞に置き換えられないか検討する習慣が、文章をより論理的で明快なものにする。
10. 骨子作成の訓練
答案を論理的に仕上げるためには、いきなり本文を書かず「骨子」を作る訓練が不可欠だ。骨子は「課題→原因→対策→効果」を一文ずつ書き出したメモでよい。これを段落順に並べれば、答案の設計図になる。試験直前期は過去問を使い、制限時間内に骨子だけを10本作る練習をすると構成力が飛躍的に高まる。
11. 論理を強化する追加テクニック
①**MECE(漏れなくダブりなく)**を意識する:根拠や対策が重複しないよう整理する。
②優先順位をつける:全てを列挙するのではなく、重要度順に提示する。
③因果関係を見える化する:矢印やフローのイメージを頭に描き、段落の流れを整える。
これらを意識するだけで、答案の読みやすさが格段に向上する。
12. 実務と試験をつなげる
論理的思考力は試験対策に留まらず、実務でも大きな武器になる。報告書作成、会議での説明、顧客への提案。いずれも「結論→根拠→効果」の流れを踏まえることで説得力が高まる。技術士試験の勉強を通じて磨いた論理的構成力は、実務に直結するスキルだ。
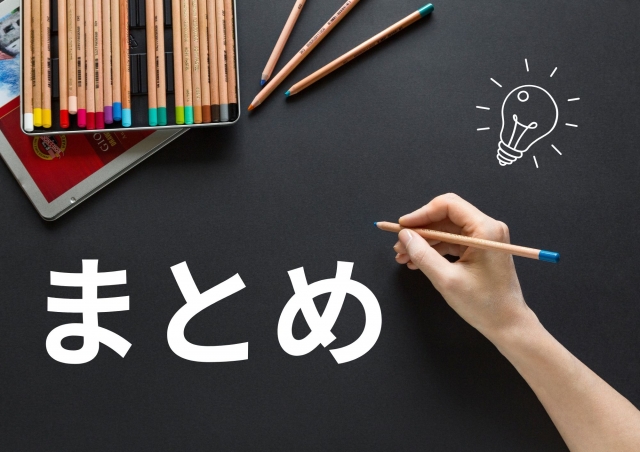
まとめ(後編)
論理的思考能力は、結論と根拠をつなぐ力に加え、それを答案全体に展開する「構成力」によって完成する。導入で軸を示し、課題・原因・対策・効果の流れを因果で貫き、結論で再主張する。この枠組みを守れば、採点者は安心して読み進められる。接続語や骨子作成といった実践的な技術を組み合わせれば、答案は一段と力強くなる。
技術士試験における論理的構成能力は、鍛えれば必ず伸びる。読解力で題意を掴み、論理的思考で筋を通し、作文力で伝える。この三位一体のうち、論理的思考と構成力を徹底的に磨くことが、合格への最短ルートである。