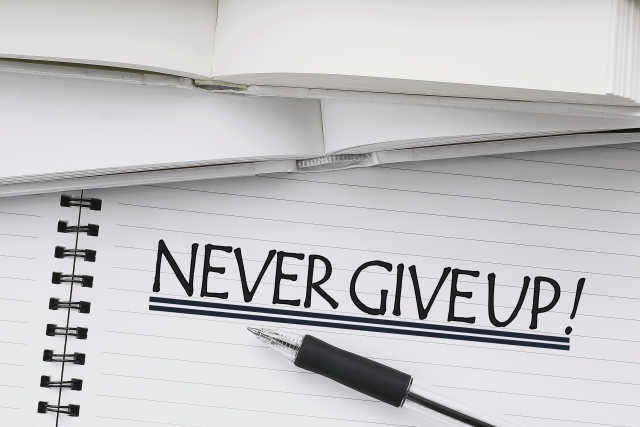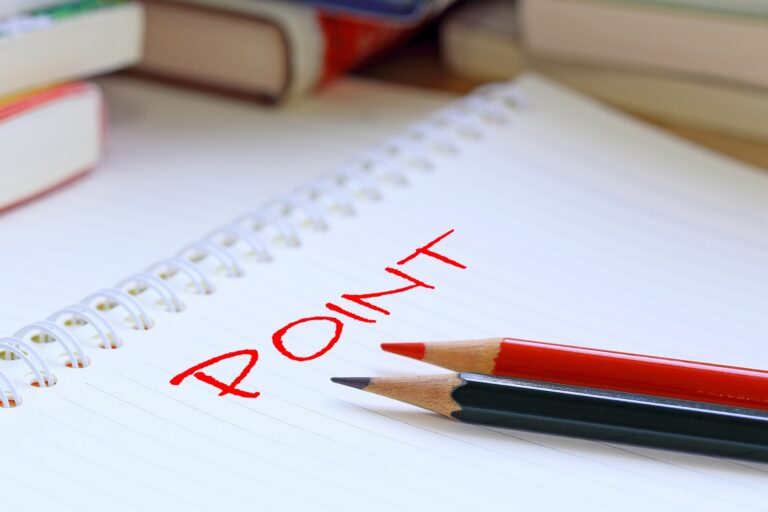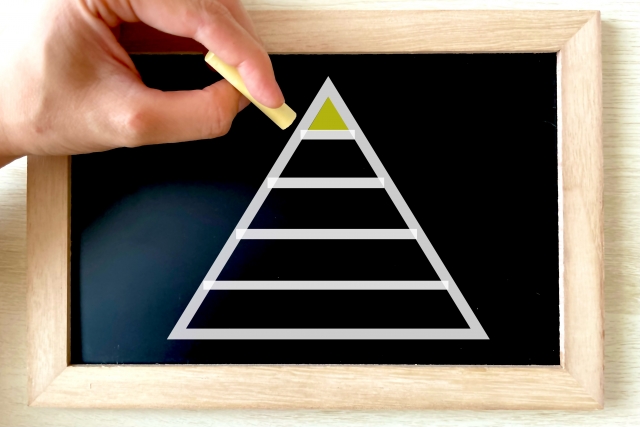前編では、日本のGX戦略の背景と主要エネルギー政策の全体像を解説しました。後編では、その戦略を具体的に社会実装するための「法律」と、2024年末に示された最新の「未来図」に焦点を当てます。法律の名称や具体的な制度に言及することで、論文の具体性と専門性が格段に向上します。

【3】GXを動かす2つの重要法律(2023年5月成立)
GXという大きな変革を国全体で進めるため、政府は法的根拠となる2つの重要な法律を整備しました。
①脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律(GX推進法)
この法律の目的は、企業が脱炭素に向けた投資に踏み切りやすくする環境を整えることです。その中核となるのが「成長志向型カーボンプライシング構想」です。
- GX経済移行債による先行投資支援: 今後10年間で官民合わせて150兆円超のGX投資を実現するため、国は「GX経済移行債」という国債を発行します。これにより、今後10年間で20兆円規模の資金を確保し、企業の脱炭素に向けた研究開発や設備投資を大胆に支援します。
- カーボンプライシングによるインセンティブ付与: 炭素排出に値付けをすることで、企業の行動変容を促す仕組みです。
- 排出量取引制度:CO2を多量に排出する企業を対象に、排出枠の売買を認める制度。
- 炭素に対する賦課金:化石燃料の輸入事業者等を対象に、CO2排出量に応じて広く負担を求める制度。
②脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(GX脱炭素電源法)
この法律は、脱炭素化された電力を安定的に供給するための体制づくりを目指すものです。再エネと原子力の両面から、制度の大きな見直しが行われました。
- 再生可能エネルギーの最大限の導入促進:
- 広域系統整備の加速:再エネ適地と大消費地を結ぶ送電網の整備計画を国が認定し、交付金制度を拡充することで、系統整備を加速させます。
- 地域との共生:太陽光発電設備の適切な廃棄を担保する制度を設けるなど、地域住民との共生に向けた事業規律を強化します。
- 安全確保を大前提とした原子力の活用: 原子力政策に関して、大きな方針転換が盛り込まれました。
- 国の責務の明確化:原子力基本法に「地球温暖化の防止」への貢献や「福島の事故を防止できなかったことの反省」が明記され、国の責務がより明確になりました。
- 高経年化炉への厳格な規制:運転開始から30年を超える原子炉は、10年ごとに設備の劣化状況を評価し、原子力規制委員会の認可を受けた長期施設管理計画の策定が義務付けられました。
- 運転期間の規律整備:運転期間は「40年」、延長は「最長20年」という原則は維持しつつ、事業者が予見しがたい事由(例:裁判所の仮処分命令や安全審査の長期化など)による停止期間に限り、60年の運転期間のカウントから除外できることとし、実質的な60年超運転を可能としました。
未来への羅針盤「GX2040ビジョン」と最新動向
「GX2040ビジョン」や「第7次エネルギー基本計画」で示された方針、特に原子力政策の転換は、論文で日本のエネルギー政策の最新かつ最も重要な動向として言及すべき事項です。
なぜ今、歴史的な政策転換が行われたのか?
「可能な限り依存度を低減」から「最大限活用」へ。この大きな方針転換の背景には、GXが目指す2つの国家的課題解決が密接に関わっています。
- エネルギー安全保障の危機感の高まり (The Growing Sense of Crisis in Energy Security) ウクライナ情勢等による化石燃料価格の急騰と供給不安は、エネルギー自給率が極端に低い日本経済を直撃しました。原子力は、一度燃料を装荷すれば長期間の運転が可能で、燃料備蓄も容易です。国産エネルギーに準ずる準国産エネルギーとして、国際情勢に左右されにくい安定したエネルギー源を確保する上で、その価値が再評価されたのが最大の理由です。
- カーボンニュートラル達成への現実的な道筋 (A Realistic Path to Carbon Neutrality) 2050年CNという高い目標を、天候に左右される再生可能エネルギーだけで達成するのは極めて困難です。電力の安定供給には、24時間365日、天候に左右されず一定の出力を維持できるベースロード電源が不可欠です。原子力は運転時にCO2を排出しないため、このベースロード電源を脱炭素化する上で、現状、最も現実的で大規模な選択肢であると判断されました。
「最大限活用」の具体的な中身とは?
「最大限活用」という方針は、以下の3つの具体的なアクションで構成されます。論文ではこれらの要素に触れると、より解像度の高い論述になります。
- ① 既存炉の再稼働 (Restarting Existing Plants):安全審査に合格した原子力発電所を、地域住民の理解を得ながら着実に再稼働させること。これが最も即効性のある対策です。
- ② 運転期間の延長 (Extending Operating Lifespans):GX脱炭素電源法に基づき、厳格な安全規制の下で既存の原子炉を可能な限り長く活用し、貴重な脱炭素電源を維持します。
- ③ 次世代革新炉へのリプレース(建て替え)(Replacement with Next-Generation Innovative Reactors):これが最も未来志向の取り組みです。廃炉が決まった原発の敷地内に、従来のものとは一線を画す、安全性・経済性を抜本的に高めた次世代革新炉を建設することを認めるものです。これは、日本が将来にわたって原子力を活用し、その技術力を維持・発展させていくという国の強い意志を示しています。

【詳細解説】まとめ:技術士論文への活かし方(実践編)
キーワードをただ並べるだけでは、良い論文にはなりません。それらを論理的なストーリーとして構成することが重要です。以下に、GX戦略をテーマにした論文の実践的な構成例を示します。
論文構成のフレームワーク
1. はじめに(背景と目的)
まず、問題の背景を国の最上位の政策から述べ、自分の立ち位置を明確にします。
- (例文)「我が国は、2050年CN達成という国際公約と、脆弱なエネルギー需給構造という国家的課題に直面している。これらを経済成長に繋げつつ同時解決する国家戦略『GX』の実現が喫緊の課題である。本稿では、技術士(〇〇部門)の立場で、GX実現に向けた技術的課題を多角的に抽出し、その解決策について論じる。」
2. 課題の抽出と分析(マクロとミクロの視点)
次に、大きな課題を自分の専門分野に落とし込み、具体的な技術課題として分析します。
- (マクロ課題)
- 課題1:エネルギー安全保障の確立:極端に低いエネルギー自給率と地政学リスク。
- 課題2:2050年CNの達成:大規模かつ変動する再エネ導入と、安定供給の両立。
- (ミクロ課題 – 自身の専門分野での具体化)
- (例:建設部門)「再エネの主力電源化には洋上風力発電が不可欠だが、我が国の厳しい気象・海象条件下での基礎構造物の設計・施工・維持管理技術の確立が課題である。」
- (例:電気電子部門)「太陽光発電の大量導入が進む一方、配電系統の安定化や調整力不足による出力抑制が頻発しており、電力系統全体の最適制御が課題である。」
3. 解決策の提示(政策と技術の連携)
最も重要なパートです。ここで国の政策や法律を根拠として引用し、自分の技術的提案の正当性を示します。
- 解決策1:再生可能エネルギーの最大限導入と系統安定化
- (政策根拠)「GX脱炭素電源法に基づく広域系統整備を加速させ…」
- (技術的提案)「…北海道・東北の豊富な風力資源を連系させるための直流送電網の整備や、需給バランスを調整するための大規模蓄電池システムの導入、VPP(仮想発電所)等の新たな制御技術の社会実装を推進する。」
- 解決策2:エネルギー安定供給と産業競争力の強化
- (政策根拠)「政府の『最大限活用』方針に基づき、安全が確認された原子力の再稼働を着実に進め、ベースロード電源を確保する。さらにGX推進法の成長志向型カーボンプライシング構想をインセンティブとし…」
- (技術的提案)「…産業部門の熱需要に対し、安価で安定的な電力を活用した電化へのシフトや、水素・アンモニアへの燃料転換を促進する。」
- 解決策3:将来を見据えた技術開発と人材育成
- (政策根拠)「将来の脱炭素電源の選択肢を確保するため、次世代革新炉の研究開発を推進し…」
- (技術的提案)「…安全性と経済性を両立するSMR(小型モジュール炉)等の技術開発を進めるとともに、これを支えるサプライチェーンの維持・強化と、次代を担う技術・人材基盤の強化に官民一体で取り組むべきである。」
4. 結論(総括と技術士の責務)
最後に、提案した解決策を要約し、技術者としての責務を述べて締めくくります。
- (例文)「以上のように、GX実現には国の政策と連携した多角的な技術的アプローチが不可欠である。私たち技術士は、倫理観に基づき、これらの技術開発の中核を担うと共に、社会への丁寧な説明責任を果たし、国民的理解を得ながらこの国家的な変革を主導していく責務がある。」