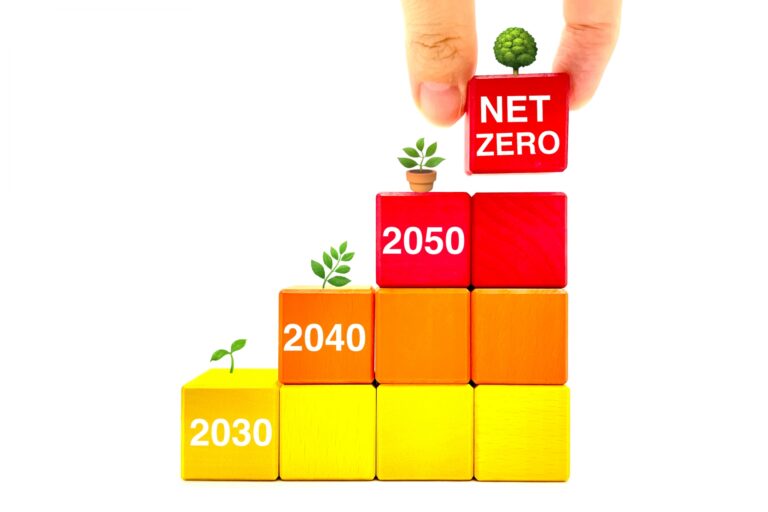技術士試験、特に筆記試験の成否は、出題された問題に対し、いかに的確な「課題」を設定し、論理的な「解」を導き出せるかにかかっています。本書『問いのデザイン』が提示する概念は、単なる質問技法ではありません。それは、技術士に求められる課題解決能力の根幹を成す思考法そのものを解き明かすものです。本稿では、本書第一章の内容を技術士試験対策の観点から再構成し、合格論文を作成するためのヒントを抽出します。

① 試験問題は「デザインされた問い」である ― 問いの設定が答えを変える
著者は、「問い」の最も基本的な性質として、「問いの設定によって、導かれる答えは変わりうる」という点を挙げています 。これは、技術士試験における問題文の読解と課題設定のプロセスに、そのまま当てはまります。出題者が提示する問題文は、まさに受験者の思考を特定の方向へ導くよう設計された「デザインされた問い」なのです。
本書で紹介されている自動車メーカーの事例は、この性質を象徴しています 。当初、クライアントが抱えていた問いは「人工知能時代に、カーナビはどうすれば生き残れるか?」というものでした 。これは、既存の製品(手段)を維持することを目的とした、視野の狭い問いです。しかし、著者(ファシリテーター)は対話を通じて、この問いを「自動運転社会において、どのような移動の時間をデザインしたいか?」へと転換させました 。
この「問いの再設計」により、議論の焦点は「製品の延命」から「人間の体験価値の創造」へと劇的にシフトしました。その結果、従来のカーナビの枠に囚われない、全く新しいプロダクトのアイデアが生まれたのです 。
これを技術士試験に置き換えてみましょう。例えば、「老朽化した社会インフラをいかに効率的に更新していくか?」という問題文が出されたとします。この問いをそのまま受け止めれば、最新の補修・補強技術やアセットマネジメント手法を論じるに留まるでしょう。しかし、ここで「問いのデザイン」を実践します。
- (元の問い)「老朽インフラをどう更新するか?」
- (転換した問い)「人口減少・激甚災害時代において、真に持続可能でレジリエントなインフラサービスを、次世代にどう提供していくか?」
このように問いを再設定することで、単なる技術論から、社会・経済・環境といった多面的な視点を含む、より高次の課題解決論文へと昇華させることができます。更新だけでなく、統廃合や機能転換、ソフト対策との連携といった、より本質的で説得力のある解決策を導き出すことが可能になります。著者が「アイデアの進化の歴史とは、問いの進化の歴史である」と述べるように 、質の高い解答の出発点は、問題文の裏にある本質を捉え、自ら「解くべき問い」を正しく立てることにあります。
② 思考と感情を刺激する ― 多角的な視点を引き出す自己への問いかけ
「問い」が持つ二つ目の重要な性質は、「思考と感情を刺激する」という点です 。問いは、単に答えを引き出すための道具ではなく、私たちの脳を活性化させ、新たな視点や好奇心を生み出すための「知的装置」として機能します。
技術士試験の論文作成において、凝り固まった思考を打破し、多面的な視点を確保するためには、自分自身に対して意図的に「問い」を投げかけることが極めて有効です。著者が「問いのテイスティング」と呼ぶワークは、その良い訓練となります 。
例えば、ある課題について考えるとき、次のように自分への問いかけを使い分けてみてください。
- 過去への問い:「この問題が発生した根本原因は何か?」「過去の類似事例から学べる教訓は何か?」
- 未来への問い:「この解決策が実現した10年後、社会はどのように変わっているべきか?」「次世代の技術者として、今から何を準備すべきか?」
- 視点を変える問い:「もし自分が市民の立場なら、この計画に何を望むか?」「もし予算の制約がなかったら、どんな理想的な解決策が考えられるか?」
こうした自問自答は、思考を特定の方向に固定せず、多角的に論点を洗い出す上で役立ちます。
さらに、動物園のワークショップで子どもたちの好奇心を爆発させた「ゾウの鼻くそはどこに溜まるの?」という事例は、問いの本質を鋭く突いています 。この問いのポイントは、問いを立てた側が答えを知っている必要はないということです 。むしろ、問い手が持つ「なぜだろう?」という素朴な好奇心と真摯な探究心が、受け手の思考と感情を最も強く揺さぶるのです 。
技術士試験においても、問題文に対して「当たり前」と思わずに、「そもそも、なぜこれが問題になっているのだろうか?」「この課題の解決によって、本当に達成したい価値は何か?」といった根源的な問いを自分にぶつけてみることが重要です。こうした「素朴な問い」こそが、他の受験者が見落としているような独自の課題発見や、斬新な解決策の着想につながるのです。

③ 対話への橋渡し ― 個人の思考から集団の知性へ
ここまで見てきたように、「問い」は個人の思考を深く、そして多角的にします。しかし、「問い」の力はそれだけにとどまりません。第三の性質として、「問いは、集団のコミュニケーションを誘発する」という点が挙げられます 。
共有された一つの「問い」は、個々人の頭の中に生まれた思考の種を、議論の場へと引き出します。そして、それらの思考が交じり合うことで、一人では到達し得なかった、より質の高い「解」が創発されるのです。
技術士論文は一人で書き上げるものですが、その思考プロセスは、**自分の中の多様な視点(専門家、市民、経営者、倫理観など)を登場させ、議論させる「一人創造的対話」**と捉えることができます。
『問いのデザイン: 創造的対話のファシリテーション』:安斎 勇樹 (著), 塩瀬 隆之(著) https://amzn.asia/d/hsSSExH