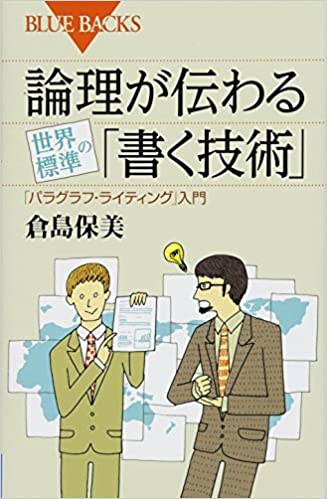目次
第一章:「平凡な知識」の本当の価値
前編では、小西甚一氏の『古文研究法』を手がかりに、技術士試験の問題文を深く正確に読み解くための「三系統の理解」について論じました。しかし、精緻な設計図を描けたとしても、それだけでは合格論文という建造物は完成しません。次に必要となるのは、その設計図に基づき、確かな材料を用いて、寸分の狂いなく構造物を組み上げていく施工能力です。
ここでもまた、小西氏の言葉が我々の進むべき道を示します。
以下『古文研究法』12ページより
「さて、こうした段階がひとわたり片づいたならば、古文の勉強はいちおう完成である。もちろん、ひとわたりではなく、幾度もくりかえして、徹底的にやりぬくことが理想的である。しかし、高校生は、国文学科の専攻学生ではない。ほかに、数学も、社会も、理科も、それぞれかなり高度の勉強を要求されている。そのなかでおこなわれる国語の勉強には、おのずから限度がある。だから、ひとわたりでよいと思う。そのかわり、その「ひとわたり」は、確実な「ひとわたり」であってほしい。一足ずつ、がっちり踏みしめてゆくのであってほしい。私がこれから述べてゆくことを、ひとわたり確実にこなすのは、あまり楽でないだろうと思う。私は、けっして難しいことを述べるつもりではない.むしろ、平凡な古文研究の常識をひとわたり説明するだけであるが、それを確実に把握し、きちんと身につけることは、なかなか容易でない。「平凡な知識を確実にこなす」、これ以外に勉強の方法はない。珍奇な知識は、いくらもある。国文学の玄人である私にとって、珍奇な知識をふりまわすことは、ステッキをふりまわすよりも容易である。しかし、諸君にとっては、ほとんど役に立たないにちがいない。珍奇な知識をおもちゃにして喜んでいるのは、実は、専門の国文学者なかまに多いのだが、諸君は、そんな関人先生のまねをするにはおよばない。知識の遊びですごすには、青春の幾年かは、あまりにも資重すぎる。」
この一節は、技術士試験の学習方法における本質を鋭く突いています。多くの受験者は、新しい技術用語やバズワード、他部門の目新しい事例といった「珍奇な知識」を追い求めることに時間を費やしてしまいます。しかし、技術士試験で本当に問われているのは、そうした知識のコレクションではありません。むしろ、自身がこれまでの実務で培ってきた「平凡な知識」を、論理の筋道の中でいかに「確実に」使いこなし、応用できるかという実践的な能力なのです。
後編では、この「確実さ」をキーワードに、思考の設計図をどのようにして堅牢な合格論文へと昇華させていくか、その具体的な方法論を掘り下げていきます。

第二章:知識を「使える力」に変える構造化
SNSや専門誌、各種セミナーでは、日々新しいキーワードが生まれては消えていきます。こうした情報を収集することは無意味ではありませんが、それをただ論文に散りばめるだけでは「切れないナイフ」でビフテキをこする行為に等しいです。小西氏が言うように、そうした知識の遊びに現を抜かすには、我々の学習時間はあまりにも貴重すぎます。
技術士試験における最も強力な武器は、あなたがこれまでのキャリアで獲得した、現場の経験に裏打ちされた知識です。それは、設計計算の一つひとつ、現場でのトラブル対応、顧客との折衝、報告書の作成といった日々の業務の中にこそ存在します。これこそが、あなただけの「平凡で、しかし確実な知識」です。
問題は、その知識をいかにして論文という公的な形式で「使える力」に変換するかです。その鍵は「構造化」にあります。構造化とは、個々の知識や経験を、前編で述べた「思考の筋道」の中に適切に位置づけていく作業です。
例えば、「インフラの老朽化対策」というテーマに対し、あなたが持つ「特定の橋梁の補修工事に携わった経験」という知識を構造化するプロセスは以下のようになります。
- 知識の抽出:経験の中から、具体的な事実を客観的に抜き出します。(例:コンクリートの剥離、鉄筋の腐食状況、採用した補修工法、その効果と限界、要したコストと期間)
- 抽象化・一般化:その個別具体的な経験を、より一般的な課題として昇華させます。(例:「橋梁の補修経験」→「コンクリート構造物の塩害対策における課題」)
- 筋道への配置:一般化した知識を、論文の論理構造の中に組み込みます。
- 課題:「インフラの点検・診断技術の高度化」
- 原因分析:「従来の目視点検では、内部の鉄筋腐食の進行度を定量的に把握することが困難であった(←自己の経験を根拠とする)」
- 解決策:「非破壊検査技術(例:電磁波レーダ法)の導入と、取得データのAIによる画像解析を組み合わせた診断システムの構築」
- 効果:「劣化の早期発見と、補修計画の最適化によるライフサイクルコストの縮減」
このように、自己の経験という「点」を、論文全体の論理という「線」の中に組み込むことで、初めて知識は説得力を持つようになります。あなたの「平凡な知識」は、構造化によって、他の誰にも書けないオリジナリティとリアリティを備えた強力な論拠へと生まれ変わるのです。
第三章:論理を積み上げる「順序」の絶対性
論文が散漫になり、説得力を失う最大の原因は何か。それは、小西氏が指摘する「勉強の筋途」の欠如、すなわち「順序の乱れ」です。
勉強の筋途を立てるという意味からは、それぞれの部分をはっきり順序だてて把握することも、もちろん必要である。
技術士論文における論理の「正しい順序」は、極めて明確です。
【題意理解 → 現状と課題 → 原因分析 → 解決策 → 評価(効果・リスク)】
この流れは、単なる答案作成上のテクニックではありません。これは、人間が物事を理解し、納得するための最も自然な思考プロセスそのものです。この黄金律を無視した構成は、読み手である試験官に不要なストレスを与え、内容を理解することを妨げます。
多くの受験者が無意識に陥る「順序の乱れ」には、以下のようなパターンがあります。
- 課題と原因の混同:「人手不足が課題だ」と書きますが、人手不足は現象(結果)であり、その原因(例:労働環境の厳しさ、若年層の入職者減少)こそが分析すべき対象です。
- 原因分析を省略した対策:課題を挙げた直後に、唐突に解決策を提示します。なぜその解決策が有効なのか、根拠となる原因分析がなければ、単なる思いつきのアイデアにしか見えません。
- 総論と各論の順序逆転:まず最初に論文全体の方向性(最も重要な課題や基本的な解決方針)を示すべきところで、いきなり個別の技術的な詳細から書き始めてしまいます。
これらの「順序の乱れ」は、思考が整理されていないことの証左であり、技術者としてのマネジメント能力に疑問符を付けさせる致命的な欠陥となります。小西氏が「一足ずつ、がっちり踏みしめてゆくのであってほしい」と説くように、論理のステップを一つひとつ、確実に踏み固めていくこと。それこそが、簡潔でありながらも重厚な説得力を持つ論文を生み出すのです。
第四章:「正確さ」への執着が技術者倫理の礎となります
学習の最終段階において、我々が到達すべき境地は何か。それは「正確さ」へのこだわり、いや、執着と言ってもよいほどの厳しい姿勢です。小西甚一氏は、この点を妥協なく断言します。
要求するのは、つねに「正確な理解」であって、もし「だいたいの理解」も理解の中に入るとお考えの諸君があるなら、私は「正確な理解」以外は理解でないと申しあげておきたい。
この言葉は、技術者という職業の本質そのものを突いています。技術者に求められるのは、常に「正確な判断」と「正確な表現」です。設計図の数値、計算式のパラメータ、報告書の記述、その一つでも曖昧さや不正確さが紛れ込めば、それは時に人命や社会の安全を脅かす大事故につながりかねません。技術者倫理の根幹は、この「正確さ」への誠実な態度にあると言えます。
論文採点においても、この基準は厳格に適用されます。試験官は、受験者の論文を「技術者として信頼に足る人物か」という視点で見ているのです。論理に飛躍はないか、データや用語の使い方は正確か、課題と解決策は本当に関連しているか。一つでも論理的な破綻や不正確な記述があれば、「この人物は重要な判断を任せられない」と見なされ、評価は厳しくなります。「急所がはずれていたら、ほかの所が出来ていたところで、零点をつけるのは、あたりまえである」という小西氏の言葉は、決して大袈裟な脅しではないのです。
だからこそ、論文を書き上げた後、我々は自身の文章を冷徹な目で何度も見直さなければなりません。「だいたい合っている」という自己満足を捨て、細部に至るまで論理の整合性を問い、表現の正確性を磨き上げる。その地道で厳しい作業こそが、技術者としての信頼性を証明する最終関門なのです。

結論:思考の筋道を鍛えることが、未来を拓きます
『古文研究法』の序文で小西甚一氏が説いた「正しい筋途を立てる」という学問のあり方は、半世紀以上の時と、文系・理系という専門分野の垣根を越えて、現代の技術士試験に驚くほど鮮やかに通底しています。
技術士に求められる能力の本質は、小手先の知識やテクニックではありません。それは、複雑で掴みどころのない問題に直面したとき、冷静にその構造を読み解き(読解力)、論理の筋道を立てて本質的な課題を抽出し(分析力)、自らの知見と経験を総動員して実現可能な解決策を構築し(課題解決能力)、そのプロセスと結果を他者に対して正確に説明できる(コミュニケーション能力)という、一連の統合された思考力です。
その根幹をなすのが、本稿で繰り返し述べてきた「思考の筋道」を自らの内に確立することです。
- 問題文の深層を、語学的・精神的・歴史的視点から多角的に読み解く。
- 自己の経験という「平凡な知識」を、論理の骨格の中に構造化して組み込む。
- 思考の「順序」を厳格に守り、論理を着実に積み上げる。
- そして、全てのプロセスにおいて「正確さ」に執着する。
この訓練は、決して試験合格のためだけのものではありません。それは、変化の激しい現代社会において、技術者として生涯にわたって価値を創出し続けるための、最も確かな礎を築く作業です。思考の筋道を鍛えること。それこそが、技術士試験の合格を勝ち取り、さらにはその先のキャリアにおいて、より困難な課題に立ち向かい、社会に貢献していくための、最も本質的な力となるのです。
註:小西甚一(こにし じんいち、1915年〈大正4年〉8月22日 – 2007年〈平成19年〉5月26日)は、日本の文学者(日本中世文学、比較文学)。文学博士(東京文理科大学・論文博士・1954年)。筑波大学名誉教授。
古文研究法 (ちくま学芸文庫 コ 30-2)
https://amzn.asia/d/6wY9AwH