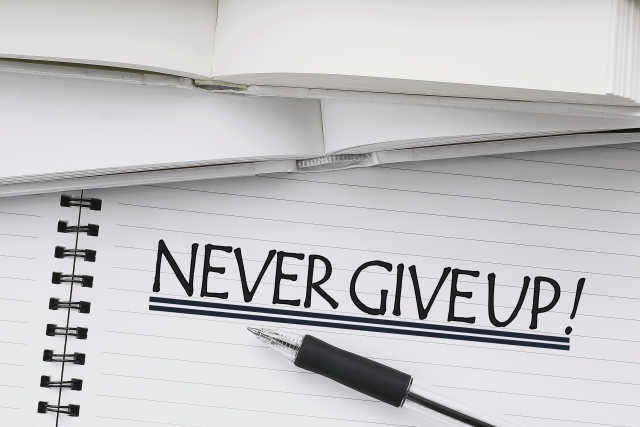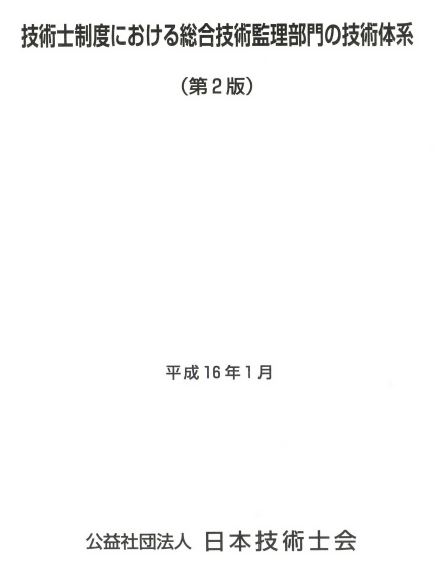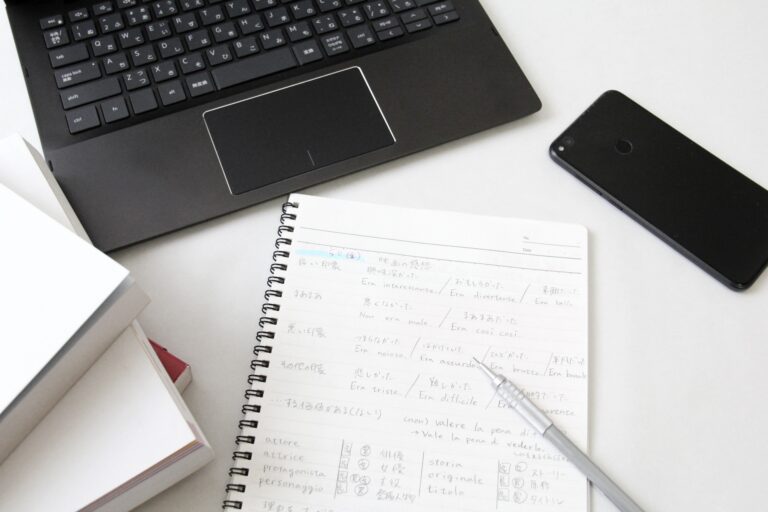技術士第二次試験の中でも、毎年最も多くの技術者が挑戦する「建設部門」。社会基盤を支えるこの分野は、技術士資格の重要性が特に高く、キャリアアップを目指す多くの建設技術者にとって大きな目標となっています。
しかし、その門戸は決して広くありません。前回の記事で見た試験全体の合格率よりも、建設部門の合格率は常に低い水準で推移しており、「最難関部門の一つ」と言っても過言ではないでしょう。
本記事では、令和3年度から令和6年度までの4年間の統計データに基づき、建設部門の合格率の推移と、その内訳である「選択科目」ごとの詳細な動向を徹底分析します。ご自身の専門分野の立ち位置を把握し、合格への戦略を練るための一助としてください。

建設部門全体の合格率推移 – 平均を下回る厳しい現実
まず、建設部門が試験全体の中でどれほど厳しい戦いであるかを、具体的な数値で見ていきましょう。
| 年度 | 建設部門 受験者数 | 建設部門 合格者数 | 建設部門 合格率 | 試験全体の合格率 |
| 令和6年 | 13,298人 | 1,152人 | 8.7% | 10.4% |
| 令和5年 | 13,328人 | 1,303人 | 9.8% | 11.8% |
| 令和4年 | 13,026人 | 1,268人 | 9.7% | 11.7% |
| 令和3年 | 13,311人 | 1,384人 | 10.4% | 11.6% |
表から明らかなように、建設部門の合格率は、毎年試験全体の平均を1~2ポイント下回っています。特に、試験全体でも合格率が低下した令和6年度には、建設部門の合格率は8.7% と、ついに9%を割り込む非常に厳しい結果となりました。
受験者数が全部門の半数以上を占める巨大部門であるため、採点基準がより厳格になる傾向があるのかもしれません。いずれにせよ、建設部門の受験者は「平均以上の厳しい戦いである」という認識を持って、入念な準備を進める必要があります。
選択科目別の合格率を徹底分析
建設部門は11の選択科目に分かれており、受験者は自身の専門分野を一つ選択します。この選択科目の選び方が、合否を大きく左右する可能性があります。ここでは、特に受験者数の多い主要な科目に焦点を当て、その合格率の推移を見ていきましょう。
▼ 主要選択科目の対受験者合格率 推移 (%)
| 選択科目 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 |
| 土質及び基礎 | 5.9% | 7.9% | 9.1% | 6.7% |
| 鋼構造及びコンクリート | 6.0% | 7.5% | 7.5% | 9.3% |
| 施工計画、施工設備及び積算 | 7.5% | 10.9% | 8.4% | 8.9% |
| 道路 | 10.8% | 10.9% | 9.9% | 11.2% |
| 河川、砂防及び海岸・海洋 | 9.4% | 10.1% | 11.5% | 11.5% |
| 都市及び地方計画 | 11.0% | 11.6% | 13.0% | 15.2% |
| 建設環境 | 12.1% | 12.9% | 12.0% | 13.4% |
このデータから、いくつかの重要な傾向を読み取ることができます。
1. 基礎分野の厳しさ:「土質及び基礎」「鋼構造及びコンクリート」
建設技術の根幹をなす「土質及び基礎」と「鋼構造及びコンクリート」は、受験者数が非常に多いにもかかわらず、合格率は常に部門平均を下回る傾向にあります。特に令和6年はそれぞれ5.9% 、6.0% と、極めて低い水準に落ち込みました。これらの科目は、専門知識の深さと正確性がシビアに問われるため、生半可な対策では突破が難しいことを示しています。令和6年度の建設部門全体の合格率低下は、これら基幹科目の難化が大きく影響していると考えられます。
2. 受験者数と合格率の逆転:「施工計画」「道路」
「施工計画、施工設備及び積算」は3番目に受験者数が多い人気科目ですが、合格率は年による変動が大きく、令和5年の10.9% から令和6年は7.5% へと大きく低下しました。一方で、同じく人気科目の「道路」は、比較的安定して10%前後の合格率を維持しています 。受験者が多いからといって、必ずしも合格しやすいわけではないことが分かります。
3. 計画・環境系の優位性:「都市及び地方計画」「建設環境」
「都市及び地方計画」と「建設環境」は、継続して高い合格率を維持している点が特徴です。これらの科目は、ハードな構造物設計とは異なり、社会的なニーズや法制度、環境配慮といった、よりマクロで複合的な視点が求められます。論文で自身の考えを展開しやすかったり、業務経験を活かしやすかったりする側面があるのかもしれません。ただし、「都市及び地方計画」の合格率は令和3年の15.2% から徐々に低下傾向にある 点は注視すべきでしょう。

まとめと考察:データが語る建設部門合格への鍵
今回の建設部門に特化した分析から、合格を目指す上で極めて重要ないくつかの傾向が明らかになりました。ここでは4つのポイントに絞り、その背景と取るべき戦略を深く考察します。
1. 建設部門は「狭き門」- 覚悟すべき競争の激化
まず認識すべきは、建設部門が技術士試験全体の中でも特に合格が難しい部門であるという事実です。過去4年間のデータを見ると、建設部門の合格率は常に試験全体の平均を1.2〜2.0ポイント下回り続けています。
- 令和6年: 建設部門 8.7% vs 全体平均 10.4%
- 令和5年: 建設部門 9.8% vs 全体平均 11.8%
- 令和4年: 建設部門 9.7% vs 全体平均 11.7%
- 令和3年: 建設部門 10.4% vs 全体平均 11.6%
受験者数が全21部門の半数以上を占めるという圧倒的な規模が、この厳しさの一因と考えられます。多くの受験者が集まるからこそ、評価基準がより厳格かつ客観的になり、わずかな差が合否を分ける厳しい競争が生まれます。特に令和6年度に8.7%まで低下したことは、これまでの対策の延長線上では通用しない可能性があるという、試験センターからの明確なメッセージと捉えるべきです。生半可な準備では合格はおろか、土俵に上がることさえ難しい、それが現在の建設部門の現実です。
2. 基幹科目は「最難関」- 求められる本質的な理解
建設部門の中でも、「土質及び基礎」と「鋼構造及びコンクリート」は、その中核をなす基幹科目です。しかし、その合格率は極めて低く、部門全体の合格率をさらに下回る「最難関」科目となっています。令和6年度の結果は特に厳しく、「土質及び基礎」が5.9%、「鋼構造及びコンクリート」が6.0% という低水準でした 。
これは、これらの科目が建設技術の根幹であるからこそ、表面的な知識ではなく、力学や材料特性に関する本質的な理解と、それを実務に応用する深い洞察力が求められるためです。計算問題では寸分の狂いも許されず、記述問題では現象のメカニズムを正確に説明できなければなりません。付け焼き刃の知識では到底太刀打ちできないこれらの科目に挑むには、専門分野の基礎を徹底的に復習し、なぜそうなるのかを常に自問自答する学習姿勢が不可欠です。
3. 科目選択が合否を分ける – 戦略的な自己分析の重要性
選択科目ごとの合格率には、顕著な差が存在します。例えば令和6年度では、「建設環境」が12.1%、「都市及び地方計画」が11.0% と比較的高い合格率であったのに対し、前述の基幹科目は5〜6%台に留まりました 。
この差は、計画系や環境系の科目が、法規制や社会情勢、合意形成といった多様な要素を複合的に論じるため、自身の経験を活かした答案を作成しやすい側面があるからかもしれません。しかし、安易に「合格率が高いから」という理由で科目を選ぶのは危険です。その好例が、人気科目の一つである「施工計画、施工設備及び積算」です。この科目は、令和5年度には10.9%の合格率でしたが、令和6年度には7.5%へと急落しました 。
ここから得られる教訓は、科目選択は自身の最も深い業務経験と専門性に合致させるべき、ということに尽きます。合格率の変動に一喜一憂するのではなく、自身のキャリアを冷静に振り返り、「これなら誰にも負けない」と自負できる分野で勝負することが、合格への最も確実な道筋となります。
4. 令和6年の著しい難化傾向とその背景
令和6年度の建設部門全体の合格率が8.7%にまで落ち込んだ最大の要因は、受験者数の多い主要科目、特に「土質及び基礎」「鋼構造及びコンクリート」「施工計画、施工設備及び積算」の合格率が一斉に低下したことにあります 。これらの数千人規模の科目が難化すれば、部門全体の平均が引き下げられるのは必然です。
これは、試験の出題傾向が、単に過去問のパターンをなぞるだけでは対応できない、より実践的で複合的な課題解決能力を問う方向へシフトしていることを強く示唆しています。一つの専門分野の知識だけでは解けない、複数の分野にまたがるような課題や、予期せぬトラブルへの対応力を試すような問題が増えているのかもしれません。
建設部門の合格を勝ち取るためには、選択した専門分野の深い知識はもちろんのこと、社会全体の動向を見据え、技術者倫理や安全管理といった共通の素養を高いレベルで身につけることが不可欠です。