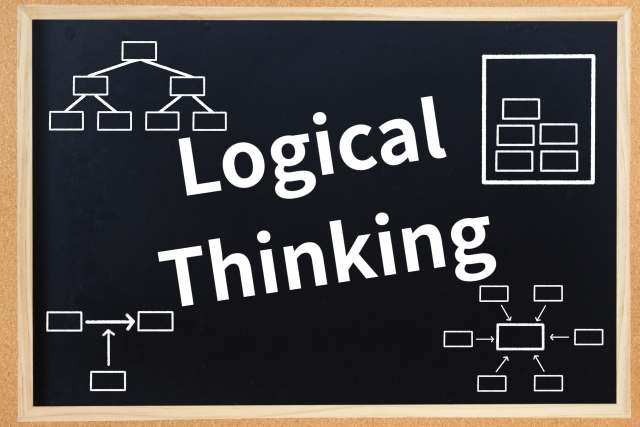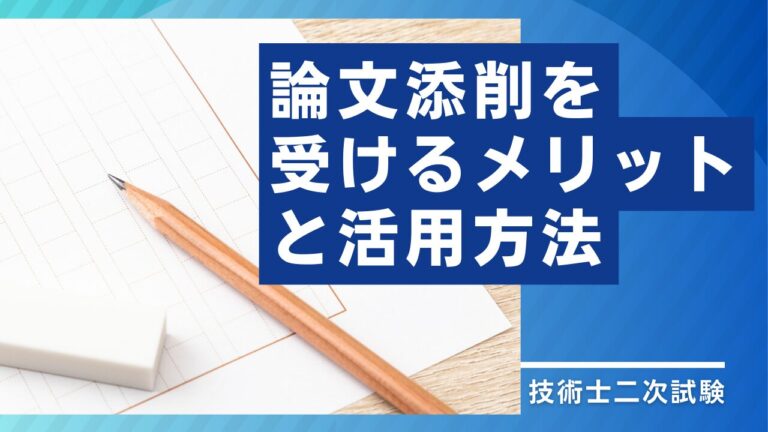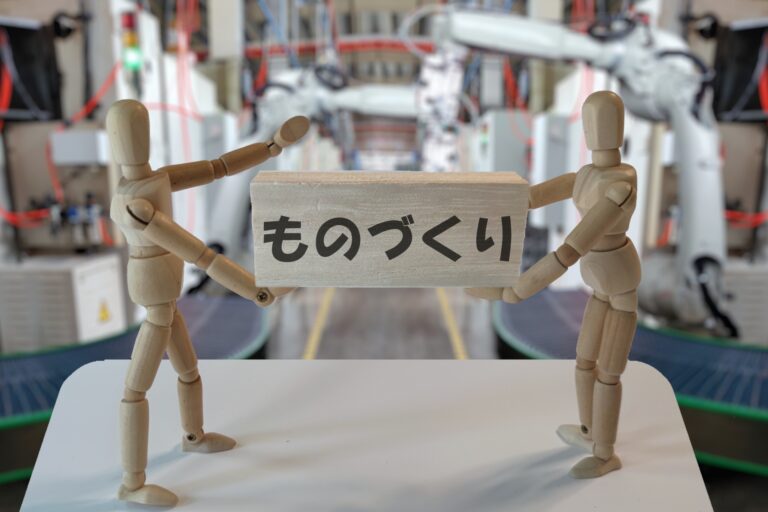技術士第二次試験は、科学技術に関する高度な専門知識と応用能力が問われる国家試験であり、技術者にとって最も権威のある資格の一つです。毎年多くの技術者がこの難関に挑戦しますが、その合格率は決して高くありません。
本記事では、令和3年度から令和6年度までの4年間の公式統計データに基づき、技術士第二次試験全体の動向を分析します。受験者数や合格率の推移、さらには受験者の属性(年齢、勤務先、最終学歴)ごとの傾向を詳しく解説し、これから受験を目指す方々へのヒントを探ります。

申込者数・受験者数・合格者数の4カ年推移
まず、試験全体の規模感を知るために、申込者数、実際の受験者数、そして最終的な合格者数の推移を見ていきましょう。
| 年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 |
| 令和6年 | 29,846人 | 23,043人 | 2,395人 |
| 令和5年 | 29,508人 | 22,877人 | 2,690人 |
| 令和4年 | 29,391人 | 22,489人 | 2,632人 |
| 令和3年 | 29,828人 | 22,903人 | 2,659人 |
申込者数は毎年約29,500人前後で安定しており、技術士資格への関心が継続して高いことが伺えます 。一方で、申込者のうち実際に受験する人の割合(受験率)は76%~77%程度です。仕事の都合や準備不足など、様々な理由で申込はしたものの受験に至らないケースが一定数存在することがわかります。
合格者数に目を向けると、令和3年から5年までは2,600人台で推移していましたが、令和6年には2,395人と、過去4年間で最も少ない結果となりました 。この背景には何があるのでしょうか。次に合格率の推移を見ていきます。
対受験者合格率の動向 – 令和6年は難化したか?
受験者数に対する合格者数の割合である「対受験者合格率」は、試験の難易度を測る上で最も重要な指標の一つです。
- 令和6年: 10.4%
- 令和5年: 11.8%
- 令和4年: 11.7%
- 令和3年: 11.6%
過去3年間、合格率は11%台後半で比較的安定していました。しかし、令和6年度は10.4%と、1.4ポイントも低下しています 。これは、単に合格者数が減っただけでなく、試験の難易度自体が上昇した可能性を示唆しています。特に、必須科目Ⅰの出題形式の変更や、より高度で実践的な応用能力を問う傾向が強まっていることなどが要因として考えられます。
この結果から、今後の受験者は、過去問の研究はもちろんのこと、社会情勢の変化や技術の最新動向を常に把握し、自身の専門分野において多角的な視点から課題を分析・解決する能力を、これまで以上に磨く必要があると言えるでしょう。
受験者の属性別分析から見える合格のヒント
次に、どのような属性を持つ受験者が合格を勝ち取っているのか、年代別、勤務先別、最終学歴別に詳しく見ていきましょう。
年代別:合格率のピークは30代
技術士試験は実務経験が求められるため、受験者の年齢層は高めになる傾向があります。
▼ 対受験者合格率の年代別推移
| 年代 | 令和6年 | 令和5年 | 令和4年 | 令和3年 |
| 20代 | 9.9% | 10.8% | 10.9% | 10.9% |
| 30代 | 12.1% | 13.2% | 13.4% | 13.5% |
| 40代 | 11.0% | 12.3% | 11.7% | 12.1% |
| 50代 | 8.4% | 10.3% | 10.3% | 9.5% |
| 60代 | 8.4% | 9.6% | 10.3% | 8.6% |
4年間のデータを通して、最も合格率が高いのは一貫して30代の受験者です 。これは、技術者としての実務経験と知識が充実し、かつ論文記述や口頭試験対策といった受験勉強に集中できる体力的・時間的な余裕を確保しやすい年代であることが理由として考えられます。
また、合格者の平均年齢は毎年42歳台で安定しています 。これは、40代の受験者層が厚く、多くの合格者を輩出していることを示しています。経験豊富な40代、50代の技術者も、知識のアップデートと論理的思考力のトレーニングを積むことで、十分に合格を狙える試験であると言えます。
勤務先別:官公庁・地方自治体の強さが際立つ
受験者の勤務先によって、合格率に違いはあるのでしょうか。
▼ 勤務先別 対受験者合格率(令和6年度)
- 官庁: 16.3%
- 地方自治体: 15.0%
- 独立行政法人等: 13.2%
- 一般企業等: 11.4%
- 建設コンサルタント業: 8.6%
データを見ると、官庁や地方自治体に勤務する技術者の合格率が突出して高いことが分かります 。この傾向は過去4年間を通して共通しています 。公共事業や政策に深く関わる業務を通じて、社会全体の課題を俯瞰し、体系的に解決策を考える能力が日常的に養われていることが、技術士試験で求められるコンピテンシーと合致しているのかもしれません。
一方で、受験者数では全体の約半数を占める「建設コンサルタント業」の合格率は、全体の平均を下回る傾向にあります 。多忙な業務の中で、いかに効率的に学習時間を確保し、論文の質を高めていくかが合格への鍵となりそうです。
最終学歴別:大学院修了者が有利な傾向
最後に、最終学歴と合格率の関係を見てみましょう。
▼ 最終学歴別 対受験者合格率(令和6年度)
- 大学院: 13.2%
- 大学: 8.8%
- 高専: 8.8%
こちらも過去4年間一貫して、大学院修了者の合格率が最も高い結果となっています 。大学院での研究活動を通じて培われる、一つのテーマを深く掘り下げ、論理的に考察し、論文としてまとめる能力が、技術士試験、特に筆記試験において大きなアドバンテージになっていると考えられます。
域のあらゆる場所で雨水を受け止める流域治水の考え方が、都市のレジリエンス向上に必須となる。

まとめ:4年間のデータから見えた合格への道筋
今回の分析から、技術士第二次試験の全体像について以下の4つの重要な傾向が明らかになりました。これらは、今後の受験戦略を立てる上で非常に価値のある指標となります。ここでは、それぞれのポイントをさらに深掘りして解説します。
1. 試験規模は安定、しかし令和6年度は難化か?
まず、試験の全体的な規模と難易度についてです。申込者数は、令和3年から6年にかけて毎年約29,500人から29,800人の間で推移しており、技術士という資格に対する安定した需要と高い関心が伺えます 。
注目すべきは、合格率の変動です。令和3年から5年までの合格率は11.6%〜11.8%と比較的安定していました 。しかし、令和6年度の合格率は10.4%と、過去3年間と比較して1.4ポイントも低下しました 。これは単なる偶然の変動と考えるより、試験内容が質的に変化し、より高度な能力を求めるようになった可能性を示唆しています。
この「難化」の背景には、単に専門知識を問うだけでなく、DX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーントランスフォーメーション)、防災・減災、インフラ老朽化といった現代社会が直面する複合的な課題に対し、技術者としていかに多角的な視点から解決策を提示できるか、という応用能力や課題解決能力をより厳しく評価する傾向が強まったことが考えられます。今後の受験者は、過去問の傾向分析だけに頼るのではなく、常に最新の社会・技術動向をインプットし、自身の専門分野と結びつけて論述できる準備が不可欠です。
2. 30代は合格の「ゴールデンエイジ」
年代別のデータでは、30代の受験者が一貫して最も高い合格率を誇るという明確な傾向が見られます。具体的には、令和3年から6年にかけて、30代の合格率は12.1%〜13.5% の範囲で推移し、常に全年代のトップに立っています 。
これは、30代の技術者が持つ以下の3つの要素が理想的なバランスにあるためと考えられます。
- 充実した実務経験: 受験資格を得てから数年が経過し、論文の中核となる業務経験の具体性と深みが増している時期です。
- 新鮮な専門知識: 大学や大学院で学んだ体系的な知識がまだ記憶に新しく、最新技術へのキャッチアップも比較的容易です。
- 学習への集中力: 20代よりも業務の裁量が増え、一方で40代、50代に比べて管理職としての責任や家庭での負担がピークに達していない場合が多く、試験勉強に集中できる環境を確保しやすい年代と言えます。
もちろん40代、50代の豊富な経験は大きな武器ですが、知識のアップデートや、現在の試験が求める論文の型に合わせて思考を整理する訓練がより重要になります。
3. 公共セクターの圧倒的な強さ
勤務先別の合格率を見ると、「官庁」および「地方自治体」に所属する技術者の合格率が突出して高いという事実は見逃せません。令和6年度のデータでは、官庁勤務者の合格率は16.3%、地方自治体勤務者は15.0%に達し、全体の平均10.4%を大きく上回りました 。この傾向は過去4年間を通して一貫しています 。
この要因として、公共事業の計画や発注、監督といった業務が、技術士試験で問われる「公共の安全確保」や「社会全体の利益」といった視点と本質的に直結していることが挙げられます。国の社会資本整備重点計画や地域のマスタープラン策定などに携わる中で、マクロな視点で課題を捉え、体系的な解決策を立案する能力が日常的に養われていることが、そのまま試験での強みとなっているのです。民間企業、特に受験者数が最も多い建設コンサルタント業(令和6年度合格率8.6%)に所属する方は 、この「公共性」や「大局的な視点」を意識的に論文に取り入れることが、合格への鍵となるかもしれません。
4. 大学院修了者が示す論理的思考の優位性
最終学歴別のデータでは、大学院修了者の合格率が大学卒の合格者を毎年大きく上回っています。令和6年では、大学院修了者の合格率が13.2%であったのに対し、大学卒は8.8%でした 。
これは単に専門知識が豊富であるという以上に、大学院の研究活動で培われる**「論理的思考力」と「論文構成能力」**が、技術士試験の筆記試験(特に必須科目Ⅰ)において絶大な効果を発揮することを示しています。修士論文や博士論文を執筆する過程で求められる、以下のプロセスは、技術士の論文試験そのものです。
- 課題の背景と現状を整理する
- 既往の研究や技術の問題点を抽出する
- 複数の解決策を立案し、比較検討する
- 最も有効な解決策を論理的に説明し、結論づける
この「研究者としての思考プロセス」を自身の業務経験に当てはめて再構築する訓練が、学歴に関わらず全ての受験者にとって有効な学習戦略と言えるでしょう。