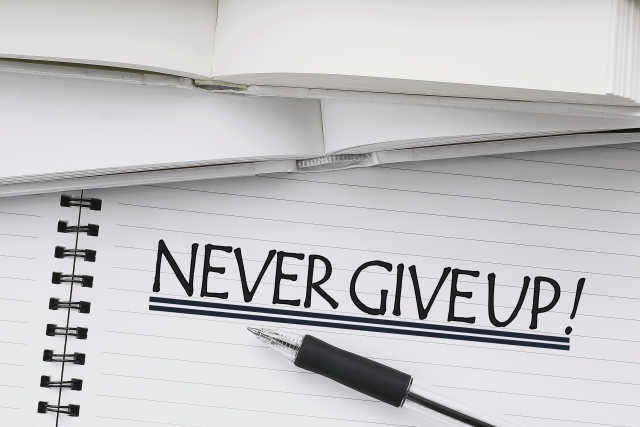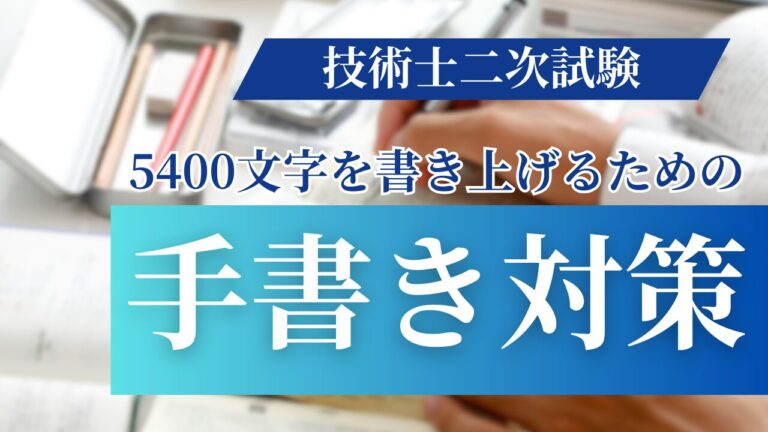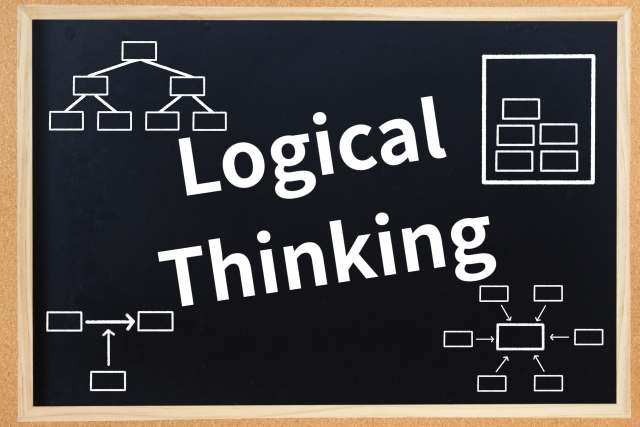1)問題文を読み解く力⇒読解力
2)論文全体を論理的に考える力⇒論理的思考能力
3)読み手に伝わる文章を書く力⇒作文力
前回までは2回に分けて「論理的思考能力」について説明しました。
今回と次回は「作文力」について、トレーニング方法までまた、2回に分けてご説明します。

技術士論文の「血肉」となる。評価を劇的に変える『作文力』の鍛え方
技術士第二次試験を目指すエンジニアの皆様、こんにちは。 前編では、技術士試験における「作文力」の本質と、その能力の欠如がもたらすリスク、そして高評価論文に共通する作文術の原則について解説しました。作文力とは、論理的な骨格に、採点官に正確に伝わる血肉を与えるための戦略的記述能力であることをご理解いただけたかと思います。
しかし、これらの原則を「知っている」だけでは、論文の評価は変わりません。重要なのは、その原則を自身の血肉とし、試験本番という極限状態で無意識に実践できるレベルまで**「できるようにする」**ことです。
本稿(後編)では、前編で解説した「高評価を得る作文術」を完全にマスターするための、具体的なトレーニング方法を4つご紹介します。さらに、記事の最後には、明日からすぐに取り組める実践練習問題も用意しました。ぜひ最後までお付き合いください。
Ⅰ:作文力を飛躍させる4つの実践トレーニング
これから紹介するのは、単なる文章練習ではありません。技術者としての思考そのものを明晰にし、それを的確な言葉に変換するための、技術士試験に特化した訓練です。
トレーニング1:『抽象→具体』変換ドリル
前編で、不合格論文の特徴として「抽象的な表現」を挙げました。この弱点を克服するための最も効果的な訓練が、この「抽象→具体」変換ドリルです。
技術論文で頻出する、一見すると正しそうに見えるが具体性に欠ける「抽象語」を、**5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)**の視点で分解し、具体的な「技術者の言葉」に変換する練習です。
- 目的: 「〜を強化する」「〜を推進する」といった、思考停止の表現を撲滅し、自身の提案に解像度と実現可能性を与える。
- 方法: 以下の例のように、抽象的な表現を具体的なアクションや数値目標を含む文章に書き換える。
【変換例1】
- 抽象: 安全対策を強化する。
- 具体: 建設現場において、AIカメラによる危険予知システムを導入し、重機と作業員の接近をリアルタイムで検知・警告することで、接触事故の発生率を前年度比で30%低減する。
- →「どのように」「何を」「どのくらい」が明確になった。
【変換例2】
- 抽象: 関係機関との連携を密にする。
- 具体: 〇〇川流域の治水対策として、国、県、市町村の河川管理者と下水道管理者が、3次元統合モデル(BIM/CIM)を基盤とした情報共有プラットフォームを構築し、降雨予測データに基づいたダム・下水管渠・調整池の統合操作計画を策定する。
- →「誰が」「何を」「どのように」連携するのかが明確になった。
このトレーニングを繰り返すことで、自身の思考の解像度そのものが向上し、論文に圧倒的な具体性と説得力を持たせることができます。
Ⅱ:トレーニング2:『一文一義』分解・再構築ドリル
前編で解説した「一文一義(一つの文には、一つの情報だけを込める)」の原則を体に叩き込むための訓練です。長い複文を自在に操る能力よりも、シンプルで短い文を的確な接続詞でつなぐ能力の方が、技術士論文では遥かに重要です。
- 目的: 主語と述語のねじれを防ぎ、論理の流れが明快な文章をリズミカルに書けるようにする。
- 方法: 新聞の社説や専門誌の解説記事など、論理的に書かれた文章の中から、少し長くて複雑な一文を見つけ出します。その文を、意味が変わらないように注意しながら、複数の短い文に分解し、その後、最も適切な接続詞を使って再構築します。
【分解・再構築例】
- 元の文: 人口減少に伴う労働力不足に対応するため、建設業界ではICT技術の活用による生産性の向上が急務であるが、多くの中小企業においては高額な初期投資が導入の大きな障壁となっているのが現状である。
- STEP1:分解(一文一義に)
- 人口減少により、建設業界は深刻な労働力不足に直面している。
- この課題を解決するためには、ICT技術の活用による生産性向上が急務である。
- 多くの中小企業が存在する。
- 中小企業にとって、高額な初期投資は大きな障壁である。
- それが導入の障壁となっているのが現状だ。
- STEP2:再構築(適切な接続詞でつなぐ)
- 人口減少により、建設業界は深刻な労働力不足に直面している。**そのため、**ICT技術の活用による生産性向上が急務である。**しかし、**業界の大部分を占める中小企業にとって、高額な初期投資が導入の大きな障壁となっている。
いかがでしょうか。再構築後の文章の方が、**「現状→課題→しかし(逆接)→問題点」**という論理構造が、遥かにクリアに読み取れるはずです。この訓練は、論理的な文章の「型」を身体で覚えるための、最も効果的な方法の一つです。
Ⅲ:トレーニング3:『なぜなぜ5回』深掘りドリル
これは、トヨタ生産方式で有名な「なぜなぜ分析」を応用した、思考の深掘りトレーニングです。論文の根拠(Reason)部分が浅薄になるのを防ぎます。
- 目的: 主張(Point)に対する理由付けを多角的かつ深層的に行い、安易な一般論から脱却する。
- 方法: 自分で作成した論文の主張(結論)に対して、「なぜ、そう言えるのか?」と自問自答を5回繰り返します。
【深掘り例】
- 主張: インフラの老朽化対策として、予防保全の導入が不可欠である。
- なぜ①? → 事後保全(壊れてから直す)では、大規模な事故につながるリスクがあり、社会的影響が甚大だから。
- なぜ②? → 損傷が顕在化してからでは、修繕コストが膨大になるだけでなく、長期の利用制限も発生し、経済活動を停滞させるから。
- なぜ③? → 橋梁の落下やトンネルの崩壊といった致命的な事故は、人命を奪うだけでなく、代替路のない地域を孤立させ、サプライチェーンを寸断するから。
- なぜ④? → 財政がひっ迫する中、今後増大する更新需要のすべてに対応することは不可能であり、事後保全を続ければ、いずれインフラ機能が維持できなくなるから。
- なぜ⑤? → したがって、限られたリソース(予算・人材)を最適配分し、インフラの長寿命化と機能維持を両立させる唯一の現実的な手段が、データに基づいた計画的な予防保全だからである。
このように「なぜ」を繰り返すことで、一つの主張の裏にある、**「安全性」「経済性」「社会性」「持続性」**といった多面的な根拠が明確になります。論文にこの深掘りのプロセスを反映させることで、思考の深さと思慮深さを採点官にアピールできます。
Ⅳ:トレーニング4:『採点官なりきり』客観レビュー
前編で述べた「読み手(採点官)意識」を養うための、最も実践的な訓練です。
- 目的: 自分の文章を客観視し、論理の飛躍、説明不足、独りよがりな表現を自ら発見・修正する能力を身につける。
- 方法: 自分で書いた答案を、一晩寝かせるなどして時間を置いた後、自分が採点官になったつもりで、赤ペンを持って厳しく読み返します。その際、以下の「悪魔のささやき」を自分に投げかけます。
- 採点官の心の声(チェックリスト)
- 「で、結局何が言いたいの?(結論は明確か?)」
- 「それってあなたの感想ですよね?(客観的な根拠やデータはあるか?)」
- 「『強化する』って、具体的にどうやるの?(具体性はあるか?)」
- 「本当にそんなことできるの?(実現可能性やリスクは考慮されているか?)」
- 「そもそも、問いに答えている?(論点がずれていないか?)」
- 「この専門用語、説明なしで伝わると思っている?(読み手への配慮はあるか?)」
この客観レビューを通じて、自分の文章の弱点を自覚し、修正を繰り返すプロセスこそが、作文力を最も確実に向上させます。

Ⅴ:実践練習問題
それでは、ここまでの内容を踏まえて、実践的な練習問題に挑戦してみましょう。解答例を参考に、ご自身の専門分野に置き換えて考えてみてください。
練習問題1:『抽象→具体』変換
以下の抽象的な文章を、あなたが専門とする分野の技術者として、具体的で説得力のある文章に書き換えてください。(100字程度)
- DXを推進し、業務の効率化を図る。
- 地域社会との連携を深め、防災力を向上させる。
- 再生可能エネルギーの導入を促進し、カーボンニュートラルに貢献する。
【解答例】
- (建設分野の例) 施工管理業務において、BIM/CIMを中核に据え、測量から検査までの全工程のデータを連携させる。これにより、書類作成時間を50%削減し、手戻りを防止することで、技術者がより創造的な業務に集中できる環境を構築する。
- (情報工学分野の例) 地方自治体が持つ避難所情報やハザードマップと、住民のスマートフォンから得られる位置情報を連携させる。これにより、災害発生時に個人の状況に応じた最適な避難ルートをリアルタイムで提示する情報システムを構築し、逃げ遅れゼロを目指す。
- (電気電子分野の例) 地域の工場や商業施設の屋根に太陽光発電設備を設置し、それらを地域マイクログリッドとして連系制御する。これにより、平時は電力の地産地消を進め、災害による系統停電時にも重要施設へ電力を供給できるレジリエントなエネルギーシステムを構築する。
練習問題2:論理構造(PREP法)の構築
以下のテーマと**結論(Point)に基づき、その間を埋める理由(Reason)と具体例(Example)**を記述し、PREP法に則った説得力のある段落を完成させてください。(200〜250字程度)
- テーマ: 気候変動下における都市型水害対策
- 結論(Point): 従来の河川改修やダム建設といったハード対策のみでは、近年の局地的豪雨による都市型水害を防ぐことは困難であり、流域全体で雨水を貯留・浸透させる「流域治水」への転換が不可欠である。
【解答例】 (P:結論) 従来の河川改修やダム建設といったハード対策のみでは、近年の局地的豪雨による都市型水害を防ぐことは困難であり、流域全体で雨水を貯留・浸透させる「流域治水」への転換が不可欠である。 (R:理由) その理由は、都市化の進展により地表面の多くがアスファルト等で覆われ、雨水の浸透能力が著しく低下しているためだ。これにより、降った雨が一気に下水道や河川に集中し、施設の処理能力を超過する内水氾濫が頻発する。 (E:具体例) 対策として、公園や学校の校庭への雨水貯留施設の整備、透水性舗装の導入、各家庭での雨水タンク設置などを官民一体で推進する。これらのグリーンインフラは、都市の保水能力を高め、河川への流出負荷を直接的に軽減する。 (P:結論の再提示) したがって、施設能力の向上だけでなく、流域のあらゆる場所で雨水を受け止める流域治水の考え方が、都市のレジリエンス向上に必須となる。
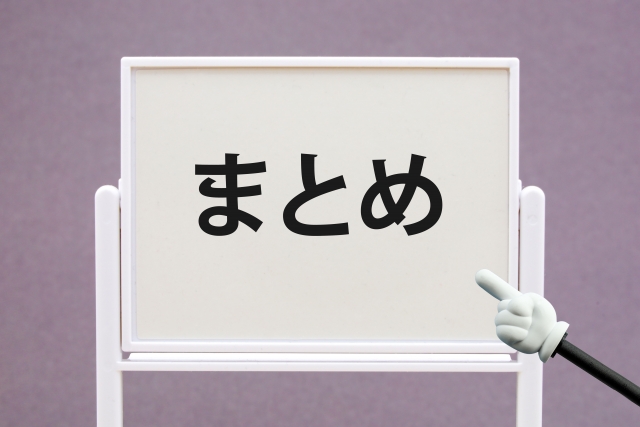
後編のまとめ
作文力は、生まれ持った才能ではありません。本稿で紹介したような、目的意識を持った**「技術(スキル)としてのトレーニング」**によって、誰でも確実に向上させることができます。
- 『抽象→具体』変換で、解像度を高める。
- **『一文一義』**で、明快さを手に入れる。
- **『なぜなぜ5回』**で、思考を深掘りする。
- **『採点官なりきり』**で、客観性を身につける。
これらの訓練は、一見地味に見えるかもしれません。しかし、この地道な繰り返しこそが、あなたの思考を整理し、それを合格論文へと昇華させるための最短ルートです。
ご紹介したトレーニングは、技術士試験のためだけのものではありません。報告書、提案書、仕様書など、技術者としてキャリアを歩む上で、生涯にわたってあなたを支える強力な武器となるはずです。
まずは一日一段落から。今日から、あなたの「作文力」を鍛え始めてみませんか。