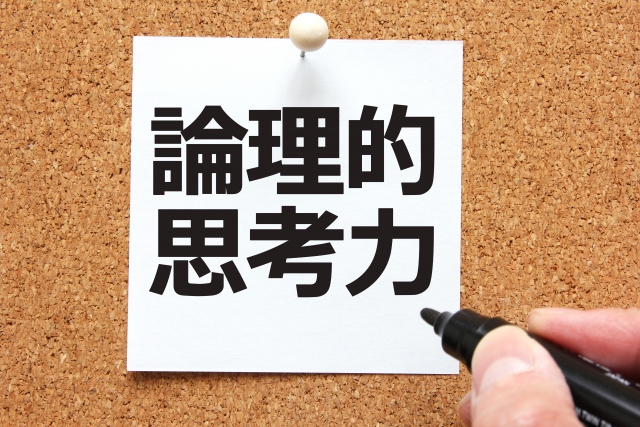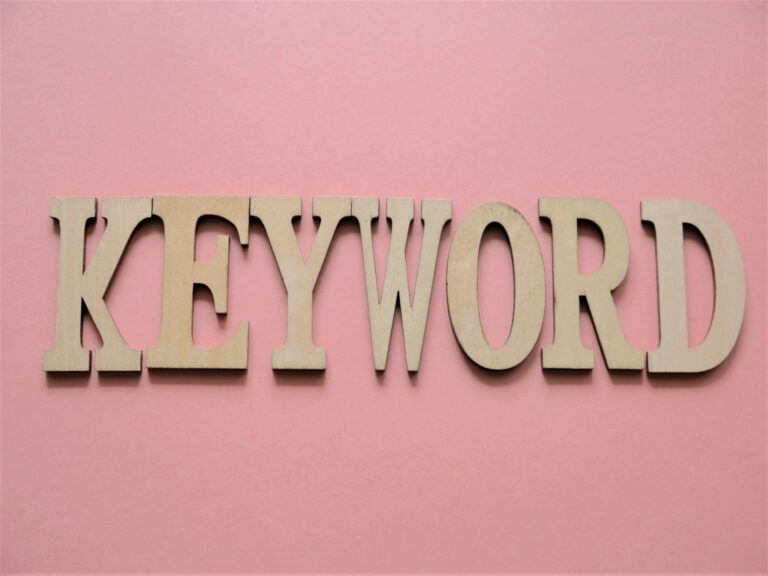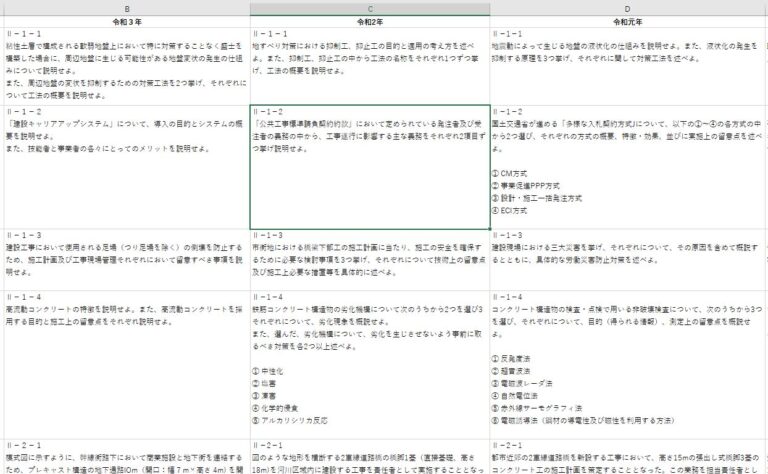技術士試験はエンジニアの試験ですが、文章の問題に対し文章で解答します。
そのため、以下3つの力をトレーニングする必要があります。
1)問題文を読み解く力⇒読解力
2)論文全体を論理的に考える力⇒論理的思考能力
3)読み手に伝わる文章を書く力⇒作文力
前回は1)の「読解力」について説明しました。
今回と次回は2回に分けて「論理的思考能力」について説明します。
以下は論文調の常体で記述します。
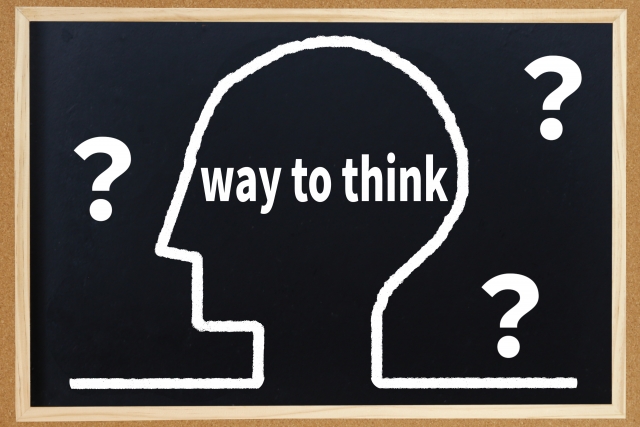
技術士試験に直結する「論理的思考能力」を鍛える(前編)
技術士第二次試験は、専門知識の量を競う試験ではない。それは、複雑化する社会課題に対し、「信頼できる思考プロセスを経て、最適な解決策を論理的に提示できるか」という、技術者としての根源的なコンピテンシーを問う試験である。
文章で問われ、文章で答えるこの試験において、合否を分ける能力が「論理的思考能力」だ。前回のテーマであった「読解力」が、顧客からの要求仕様書(問題文)を正確に読み解く力だとすれば、論理的思考能力は、その要求に応えるための**「設計図(論文構成)を描き、構造計算(論理の検証)を行う力」**に他ならない。
採点官は、受験者が持つ知識の断片そのものよりも、**「その知識をいかに体系的に組み合わせ、矛盾なく、説得力のある結論へと導いているか」**という思考の道筋を評価する。この道筋、すなわち論理が破綻していれば、どれほど高度な専門用語を並べても高評価を得ることはできない。
- 論理的な文章の「最小単位」をマスターする
これは、問題文というテキストの中から、解答の骨格となる重要な要素を正確に抜き出す能力である。- 論理的思考とは、突き詰めれば**「結論(Point)」と「根拠(Reason)」を明確に分離し、その両者を強固な橋で結ぶ**作業である。多くの不合格論文は、この基本構造が極めて脆弱だ。
- 根拠なき主張:「〇〇すべきである」という主張ばかりで、なぜそう言えるのかという客観的な根拠が示されていない。これは単なる意見や感想文であり、技術論文とは呼べない。
- 主張なき根拠の羅列: 知っている知識やデータをただ並べるだけで、「だから、何が言いたいのか」という結論が不明瞭。これでは採点官に思考の放棄と見なされても仕方がない。
- この欠点を克服するため、論文の各段落を**「一つの完結した論理ブロック」として構築する意識が不可欠である。そのための最も強力なフレームワークがPREP法**だ。
- P (Point): 主張・結論。この段落で最も伝えたい核心を、まず一文で明確に述べる。
- R (Reason): 理由。なぜその主張(Point)が言えるのか、その根拠を説明する。
- E (Example): 具体例・データ。理由(Reason)を裏付ける客観的な事実、事例、統計データなどを挙げる。
- P (Point): 結論の再提示。具体例を踏まえ、最初の主張(Point)が妥当であることを改めて示す。
- 論文を書き始める前に、まず**「何を結論とするか」を一文で定義する。そして、その結論を証明するために最適な「理由」と「具体例」は何か、と逆算して思考する**訓練が、論文全体の強固な背骨を創り上げる。
- 「なぜ問題文の冒頭でこの法改正に言及しているのか」
- 「このキーワードとあのキーワードは、どういう関係性で結びついているのか」
- 「『持続可能』という言葉に出題者はどのような意味を込めているのか」
といった問いを自らに投げかけ、出題者がどのような論文を「良い評価」とするかを読み解いていくプロセスである。
- 論理展開の「型」を自在に使い分ける
結論と根拠を結びつける論理展開には、代表的な「型」が存在する。これを意識的に使い分けることで、文章の説得力と分かりやすさは飛躍的に向上する。技術士論文で特に重要なのが、**「演繹法」と「帰納法」**の二つである。
演繹法(トップダウンアプローチ)
演繹法とは、「誰もが認める大原則やルール」から出発し、それを特定の状況に当てはめて、必然的な結論を導き出す思考法である。思考の方向が「大
→小」へと進むため、トップダウンアプローチとも呼ばれる。
●構造: 大原則(ルール)→ 具体的な状況(観察事項) → 結論
●身近な例:「空を見て、傘をさす」思考
・大原則: 「黒い雲は雨の兆候であり、雨が降れば濡れるので傘が必要だ」
・具体的状況: 「今、空に黒い雲が広がっている」
・結論: 「したがって、外出するなら傘を持っていくべきだ」
この論理展開は、前提となる大原則が正しい限り、結論もまた正しくなるため、極めて説得力が高い。
●技術士論文での活用例(テーマ:インフラの維持管理)
・大原則(社会的要請・規範): 公共インフラは、対症療法的な事後保全ではなく、計画的な予防保全によってライフサイクルコストを最適化し、国民の安全を確保することが求められる。
・具体的状況(事実・データ): 我が国の橋梁やトンネルの多くは高度経済成長期に集中建設されており、今後20年で建設後50年を超える施設の割合が加速度的に増加する。
・結論(導き出されるべき方策): したがって、限られた予算と人員の中でインフラの機能不全を回避するためには、従来の修繕型管理から、点検・診断技術を高度化し、データに基づいた予防保全へと抜本的にシフトすることが急務である。
演繹法は、論文の中心的な主張や、課題に対する解決策を力強く提示する場面で絶大な効果を発揮する。
帰納法(ボトムアップアプローチ)
帰納法とは、「複数の具体的な事例」を観察し、そこから共通するパターンや法則性を見つけ出し、一般的な結論を導き出す思考法である。思考の方向が「小→大」へと進むため、ボトムアップアプローチとも呼ばれる。
●構造: 複数の具体例→ 共通点・法則性 → 結論(一般化)
●身近な例:「名探偵の推理」思考
・具体例①: 「現場Aで、ある特定の痕跡が見つかった」
・具体例②: 「被害者Bの関係者リストに、同じ特徴を持つ人物がいた」
・具体例③: 「過去の類似事件Cでも、同様の手口が使われていた」
・結論: 「これらの事実から、犯人は〇〇という特徴を持つ人物である可能性が極めて高い」
帰納法によって導かれる結論は、100%絶対とは言えないが、十分な数の信頼できる事例に基づいている場合、高い確からしさを持つ。
●技術士論文での活用例(テーマ:建設現場の生産性向上)
・具体例①: A社では、ドローンによる3次元測量を導入した結果、測量にかかる人員と時間を80%削減した。
・具体例②: B現場では、ICT建機を活用することで、若手技術者でも熟練工と同等の精度での施工が可能となり、手戻りが大幅に減少した。
・具体例③: Cプロジェクトでは、BIM/CIMを導入して関係者間の合意形成をフロントローディングした結果、設計変更が60%減少し、工期を15%短縮した。
・結論(導き出される一般論): これらの成功事例に共通するのは、デジタル技術を活用して「測量・施工・管理」の各プロセスを効率化・省人化している点である。よって、建設業界全体の生産性を向上させるためには、i-Constructionに代表されるデジタル技術の積極的な導入と普及が有効な手段である。
帰納法は、課題の背景や現状を客観的に説明する場面や、自らが提唱する解決策の妥当性を複数の事例で裏付ける場面で使うことで、論文に厚みと客観性を与える。
なお、「仮説推論」は、限られた情報から「おそらくこれが原因だろう」という最も確からしい仮説を立てる思考法であり、論文の「課題抽出」の段階で無意識に使っていることが多い。論文の論理展開の主軸は、あくまで演繹法と帰納法で組み立てるのが基本である。
これらの論理の「型」は、単なる文章テクニックではない。それは、技術者としての思考を整理し、加速させるための**オペレーティングシステム(OS)**である。このOSを自身の思考にインストールすることで、どんな複雑な問題が来ても、迅速かつ的確に処理できるようになる。まずは過去問を分析する際に、「この段落は演繹法で書かれているな」「この主張は帰納法で裏付けるべきだな」と意識することから始めてほしい。それが、合格論文への最短ルートとなる。し、解釈する能力である。 - 論点の多角化と構造化
論理的思考では、多角的な視点から論点を補強することが重要だ。しかし、それは「単なる羅列」ではなく、結論との関係を整理した構造の中で行うべきだ。例えば「経済性・人的資源・情報・安全・社会環境」という五管理を答案に盛り込む場合、それぞれが結論にとって「必要条件」なのか「十分条件」なのか、「補完関係」なのかを明示する。こうして関係性を整理すると段落の順序も自然に決まる。向き合うか」を深く考える能力である。 - 題意との整合性を意識する 設問には必ず目的語がある。「課題を述べ、対策と効果を示せ」とあれば、課題=現状不一致、対策=原因に作用する処置、効果=測定可能な成果である。課題を抽象化しすぎると対策が標語になるし、対策から書き始めれば論点先取になる。まず「設問の目的・制約・評価軸」を答案冒頭で短く宣言し、その中で課題→原因→対策→効果を因果鎖として一本通す。これが「題意に沿った答案」になる。
- 因果と相関を区別する データを根拠に使う際は「時間順序」「第三要因」「メカニズム」の3点を確認する。例えば「DX導入で生産性が上がった」と書くなら、導入前後の条件、他の施策の影響、具体的な改善プロセスを示す。因果が断言できなければ「相関の示唆」と正直に書き、意思決定には「試行導入とモニタリングで検証」と添える。これだけで答案の信頼性が大きく上がる。
- 反論への先回り 論理を強化する方法は「反論を内包する」ことだ。例えば「更新計画は効果的だが初期費用が大きい」という弱点を自ら認め、「よってフェーズ分割と投資基準を設定する」と処理する。弱点を外部に残さず内部で吸収すれば、結論の現実性が跳ね上がる。
- 構造化の技法 ピラミッド原則は答案構成の強力な武器である。冒頭で結論を宣言し、根拠を三つにまとめる。それらを「強度順・因果順・時間順」など意味のある順序で並べ、各根拠を事実→意味→含意の流れで展開する。テンプレートとしては「導入(題意+評価軸)→本文三段(根拠ごと)→結論(再主張+効果指標)」の型を徹底する。この型を使えば、どの分野の答案でも破綻しない。また、ロジックツリーは原因追及と解決策検討の両方で有効だ。原因なら「なぜ」を三回掘り、対策なら「資源・プロセス・技術・ガバナンス」に分ける。葉の粒度を揃えないと段落の重さに差が出て読みにくくなるため、訓練として下書きに簡易ツリーを描く習慣を持つとよい。
- 定量的根拠を入れる 論理を強めるには数値が不可欠だ。効果を示すKGI、進捗を示すKPIを答案に組み込む。漏水対策なら「年間漏水量」「破裂件数」「更新コスト当たり削減量」などを指標にする。数値は概算でもよく、前提を示せば十分説得力を持つ。
- よくある論理破綻の回避 論理的思考力を高めるには、自分の答案の誤りを潰す視点が重要だ。循環論法、論点先取、過度の一般化、二分法の罠、権威への依存。これらを最後のチェックリストとして段落冒頭と結論を読み直せば、致命的な破綻は避けられる。
- 試験本番での思考手順 ①設問を要約して題意を一文にする ②評価軸と制約を抽出する ③結論を仮置きし、根拠を三つ選ぶ ④反論と管理策を一つ加える ⑤段落冒頭文だけ先に書き、そこに具体例や数値を入れる この流れを定着させれば、答案の論理は大きく崩れない。
- トレーニング方法 過去問を使って次の訓練を繰り返す。 ・設問要約(1文) ・評価軸の抽出 ・結論(1文) ・根拠(3点) ・反論と管理策(1点) ・効果指標(2点) これを15分で下書きする。慣れたら時間を短縮し、精度と速さを同時に高めていく。
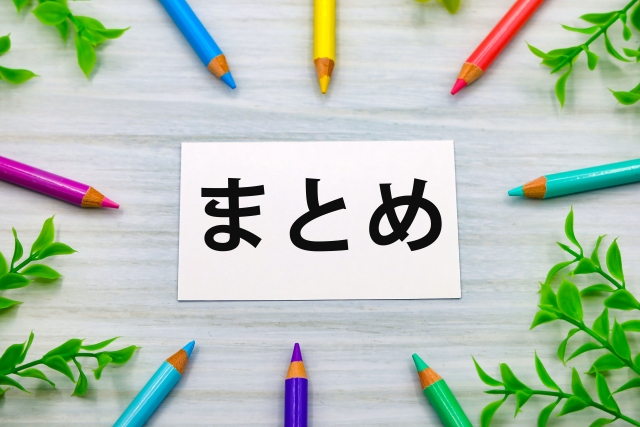
まとめ(前編)
論理的思考能力は才能ではなく、型を理解し、結論と根拠を整理し、数値と反論を織り込み、題意に従って展開することで誰でも鍛えられる。今回はその土台を解説した。次回はこの基盤を実際の答案構成へと接続し、段落設計や接続語の使い方、具体的なテンプレートまで踏み込む。採点者を迷わせない答案を仕上げるために、さらに実践的な技術を解説していく。